第115回 自社株買い実施が6兆円を超えた!(2018年度)
3分でわかる 新社会人のための経済学コラム2019年9月2日
「自社株買い」

最近、自社が過去に発行した株式を企業自身が買取る「自社株買い」を行う企業が増えています。2018年度の東証1部上場企業の自社株買い実施額は、6.1兆円でした。
2015年度の5.5兆円(※1)を超えて、過去最高を更新しています。
このように、企業の積極的な自社株買いが増えている背景には、企業価値向上に必要とされるコーポレート・ガバナンス(企業統治)改革があります。
-
(※1)2015年度の自社株買いについてのコラムはこちら

(資料)QUICKより筆者作成。2019年度は5月末時点。
「稼ぐ力」
コーポレート・ガバナンス改革では、企業が株主等の利害関係者との適切な対話のもと、経営を実行することで、中長期的な収益性・生産性の向上、つまり企業の「稼ぐ力」をあげることを目指しています。
コーポレート・ガバナンス改革によって、株主は企業の「稼ぐ力」に、より厳しい目を向けるようになり、企業は、株主から集めた資本(お金)を効率よく利益拡大に活用することが求められています。ROE(自己資本利益率)は、企業が資本をいかに効率的に活用しているかを表す代表的な指標の一つです。
図表2はROEの計算式です。分子の利益が増加すると、当然ながらROEは上昇しますが、自社株買いを行うことでも分母の自己資本が減少し、ROEは上昇します。そのため、当面の有効な投資先が見つからない場合などに、株主への利益還元を図る意味もあり、自社株買いを行う企業が増えているのです。
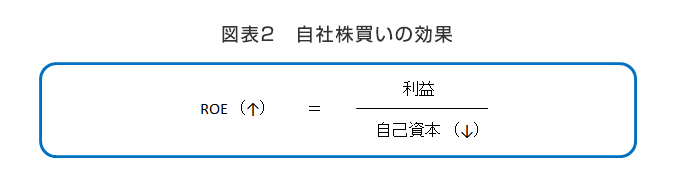
なお、自社株買いは、経営者が自社の株価が割安(もっと価値が高い)と示す意味もあり、自社の株価が低迷する際に株価を下支えるアナウンスメント効果も、企業側は期待していると考えられます。
また、コーポレート・ガバナンス改革では、政策保有株も課題視されています。その解消方法に自社株買いが用いられていることも、自社株買いが増えている理由の一つです。政策保有株とは、買収防衛策や取引先との関係強化のために、2つ以上の企業がお互いに持ちあっている株式のことです。2018年に改訂された、企業の行動指針をまとめた「コーポレート・ガバナンス・コード」では、政策保有株について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクを具体的に精査し、検証した内容を開示することが求められています。保有の適否を検討した結果、政策保有株を売却する場合に、株式市場で売却すると株価を押下げる可能性が高いため、発行元の企業は、自社株買いを行うことで売却分を吸収し、株価への影響をできるだけ抑えようとしています。
2019年度の自社株買い実施額は、4〜5月の2カ月間で3.6兆円と、すでに昨年度の50%を超える額が発表されています。今年度も引続き、自社株買いの実施額は増えると予想され、株式市場を見る際のキーワードの一つとして注目してみるのも面白いかもしれません。
(ニッセイ基礎研究所 森下 千鶴)
筆者紹介

森下 千鶴(もりした ちづる)
株式会社ニッセイ基礎研究所、金融研究部
研究・専門分野:株式市場・資産運用
