第114回 外国人労働者は146万人。今後5年間で最大34.5万人を受入れ。
3分でわかる 新社会人のための経済学コラム2019年8月1日
外国人労働者の現状

日本で働く外国人労働者は増加しています。厚生労働省によると、2018年10月末時点における外国人労働者数は146万人。同時期における日本の就業者数が6,725万人であることから、働く人の100人に2.2人が外国人ということになります。
外国人労働者を出身国別に見ると、中国(38.9万人、26.6%)、ベトナム(31.7万人、21.7%)、フィリピン(16.4万人、11.2%)の順に多く、ベトナムからの労働者数が大きく伸びています。近年の増加は、日本語学校で学ぶ留学生や日本の製造技術を学ぶためにやってくる技能実習生が中心です。彼らの多くはパートやアルバイトなど、特別な技能や経験を必要としない、いわゆる単純労働に従事していると言われています。

(資料)厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況表一覧」をもとにニッセイ基礎研究所作成
増加の背景
外国人労働者が急増している背景には、国内の人手不足があります。日本銀行「短観」の雇用人員判断D.I.を見ると、多くの産業で数値がマイナスとなっていることが分かります。これは、人手不足の現状を示すものであり、とりわけマイナス幅の大きな建設、宿泊・飲食サービス、対個人サービス(医療・介護などを含む)などでは、人手不足が深刻な問題となっています。貴重な労働力として、外国人労働者への期待が高まっているのです。
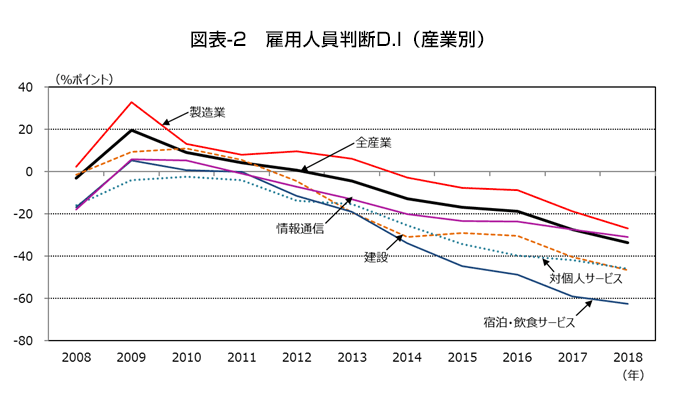
(注)全規模・四半期データの平均値。
(資料)日本銀行「短観」をもとにニッセイ基礎研究所作成
今後の見通し
政府は人手不足の深刻化に対処するため、2019年4月から「新たな在留資格制度(特定技能1号および2号)」を創設しています。この制度では、特に人手不足が深刻とされる14業種を選定し、今後5年間に最大34.5万人の外国人労働者を受入れることを見込んでいます。
初年度となる今年は、新たな領域で3.3万人から4.8万人を受入れることを想定しています。ただし、制度開始までの期間が短かったこともあり、試験日程が決まらないなど、受入準備が十分にできているとは言えない状況です。初年度については、想定より少なくなることもありそうです。
一方で、対象業種については、今後拡大していくことも考えられます。検討初期に5業種(介護、宿泊、建設、造船、農業)に留まっていた対象業種は、業界団体などの要望を受けて14業種まで拡大しています。
また、新たな資格(特定技能1号)へ無試験で移行できる技能実習も、これまで対象職種を広げてきました。今後、皆さんが働く業界でも、外国人労働者の受入れが進んでいくかも知れません。
ここまであまり触れて来ませんでしたが、新たな在留資格制度には課題も多くあります。中でも、外国人労働者との共生をどのように実現するか、という課題は大変重要です。労働者としてだけでなく、生活者としての外国人をどのように受入れていくのか。これからも試行錯誤を続けていく必要がありそうです。
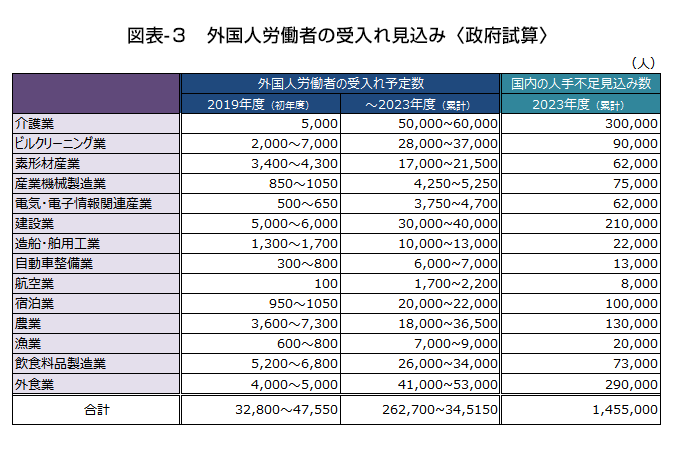
(資料)各種報道をもとにニッセイ基礎研究所作成
(ニッセイ基礎研究所 鈴木 智也)
筆者紹介

