第113回 7月のUV-B紫外線量は12月の4.3倍もある!〜日焼け止めクリームを3時間ごとに塗り直すことが大事!〜
3分でわかる 新社会人のための経済学コラム2019年7月1日
7月のUV-B紫外線量は12月の4.3倍もある!

7月に入り、強烈な日差しが照りつけていることと思います。ところで新社会人の皆さんは、日焼け対策をきちんとされていますか?漠然と紫外線は皮膚に良くないから、とりあえず毎日日焼け止めクリームを塗っておけば良いのだろうと考えてはいませんか?
今回は、日常の日焼けにより引き起こされる皮膚傷害や正しい紫外線対策についてご紹介します。
そもそも紫外線とは?
紫外線とは太陽光(日射)の一部であり、波長により3種類に分けられています。その多くが地表に届き、長時間浴びると健康影響が懸念されるUV-A、オゾン層の変化に伴い紫外線量が変化し、日焼けや皮膚がんの原因ともなるUV-B、空気中の酸素分子とオゾン層に遮られて、地表には到達しないUV-Cがあります。
また、薄い雲の時にはUV-Bは80%以上透過し、屋外では太陽から直接届く紫外線量とほぼ同程度を浴びることになります。さらに、コンクリートやアスファルト上では10%程度の反射率があり、日常生活を送る中で必ず浴びているものです(環境省、2015)。
気象庁が発表している「月別紫外線照射量」によりますと、UV-Bの値は1月から段々増加し始め、7月になるとピークに達していることが分かります(図1)。東京の7月UV-B紫外線量の値は7.3kJ/m²に昇り、12月の1.7kJ/m²のおよそ4.3倍にもなります。また、7月の時刻別のUV-B紫外線量は、地域別に多少差はありますが、正午になって最も多くなっています(図2)。そのため、7月、特に正午前後には入念に紫外線対策をする必要があるのです。
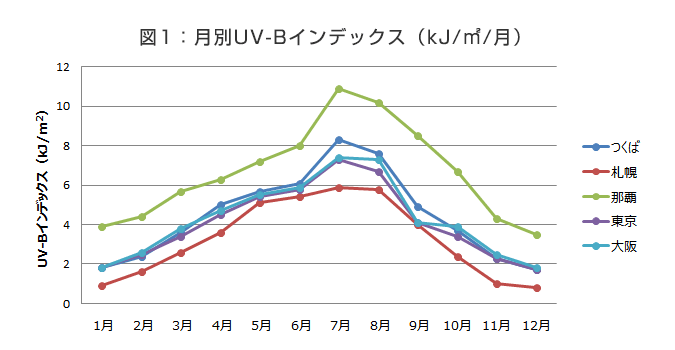
注)札幌・つくば・那覇は気象庁観測点による2017年の実測値であり、東京・大阪は衛星による2018年解析値(1時間積算値)である。
出典)気象庁(2019)「日最大UVインデックス月平均値及び日最大UVインデックス(解析値)」より筆者作成
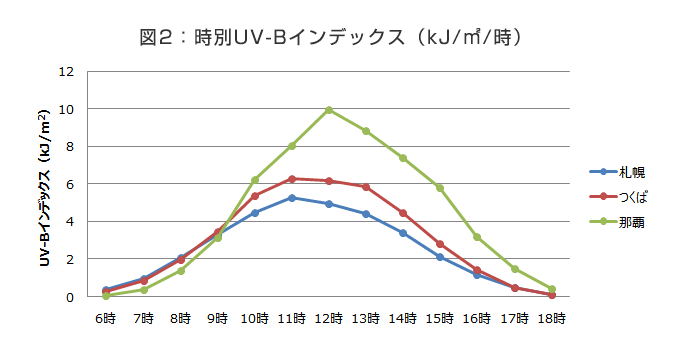
注)時別UV-Bインデックスの値は、3観測点(札幌・つくば・那覇)のみ公表されているため、東京・大阪の値は記載していない。また、各観測点全てのデータが揃う2017年7月1日〜7月31日までの実測値を平均したものである。
出典)気象庁(2019)「大気・海洋環境観測年報」より7月平均値筆者作成
日焼けによる皮膚傷害とは?
人間の皮膚は、表皮、真皮及び皮下組織からできています。表皮は皮膚の最も外側にあり、メラニン色素を生成する色素細胞や免疫機能を司る機能を持合せています。
この表皮の色素細胞が生成するメラニンは、紫外線を吸収してDNAへのダメージを抑える光線防御機能を担っています。しかし、紫外線を長期に浴びたり、日焼け対策が不十分な場合には、皮膚の炎症として急性傷害と慢性傷害が引き起こされる恐れがあります。
急性傷害である日焼けは、紫外線をあびて数時間後に皮膚が赤くなる「サンバーン」と、皮膚が赤くなる状態が消失した後に、皮膚が黒っぽくなる状態が数週間から数カ月続く「サンタン」に区分することができます。サンバーンは、日光照射から数時間後にヒリヒリとした炎症が8時間から24時間をピークに引き起こされ、2、3日で消失しますが、酷い時には水ぶくれが現れます。一方、サンタンは、紫外線により色素細胞が刺激されたことで、メラニンの大量生成が引き起こされ、単純ヘルペスや光線過敏症などの様々な症状が引き起こされます。いずれも、事前の日焼け止め対策や炎症後の早期冷却などが有効であると知られています。
慢性傷害では、紫外線を長年浴び続けると、DNAの修正間違いなどが引き起こされ、日光硬化症から有棘細胞がんなどの皮膚がんに繋がる可能性があります。これらの皮膚がんはUV-Bとの関連性が高いため、UV-Bの特性を考慮して対策することが重要とされています。統計的には、日本人の皮膚がん罹患率は人口10万人あたり14〜16人(国立がん研究センター、2017)と多くはないですが、オゾン層破壊による紫外線量の変化や平均寿命の延伸による累積紫外線暴露量の増加などが懸念されるため、将来の皮膚がんを予防するためには、日ごろからの適切な紫外線対策が重要なのです。
日ごろからの紫外線対策
主な紫外線対策には、日焼け止めクリームの塗布や、日傘の使用、UV防止パーカーの着用などがあります。特に、日焼け止めクリームは最も身近な紫外線対策となりますが、正しい使用が重要となります。
日焼け止めクリームに記載されているSPF(Sun Protection Factor)は、日焼けによる皮膚へのダメージをどの程度(倍)遅らせることができるかを示しています。SPF1はUV-Bを約20分防ぐとされています。皮膚へのダメージを受ける時間には個人差がありますが、平均約20分前後とされているため、SPF10だと、20分×10倍=200分(3時間20分)皮膚へのダメージを遅らせることができます。また、PA(Protection Grade of UV-A)は、UV-Aを防ぐもので、+の数が多いほど効果が強いことを意味しています。
ここで、注意したいのは、SPFもPAも値が高いものほど皮膚への負担が大きいことです。日焼け止めクリームに含まれる紫外線吸収剤と紫外線散乱剤に対してアレルギー反応がみられる場合があります。日常の紫外線対策だと、屋外に3時間も出ない場合は、SPF10のPA+の使用で十分です。心配な場合は、SPF10のPA+の日焼け止めクリームを3時間ごとに塗り直すことをお勧めします。さらに、日焼け止めクリームを塗る代わりに、皮膚への負担が少ない、サングラスや帽子、UV防止衣類などの着用も効果的です。
紫外線対策は、皮膚傷害や皮膚がんの予防のために大変重要なことですが、数値の高い日焼け止めクリームを選択すれば良いというものではありません。新社会人の皆さんも、ご自身の通勤時間や営業などの外まわりの時間帯などを考慮して、なるべく皮膚への負担が少なく、日焼け止め効果も適切に見込めるものを選択するようにしましょう。
【参考・引用資料】
- 環境省(2015)「紫外線 環境保健マニュアル2015年3月改定版」
- 気象庁(2019)「日最大UVインデックス月平均値及び日最大UVインデックス(解析値)」
https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/uvhp/info_uv.html - 気象庁(2019)「大気・海洋環境観測年報」
https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/data/report/data/ - 国立がん研究センター(2017)「最新がん統計 部位別がん罹患率(全国合計値2014データ報告)」
(ニッセイ基礎研究所 乾 愛)
筆者紹介

乾 愛(いぬい めぐみ)
株式会社ニッセイ基礎研究所
生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任
研究・専門分野:医療・健康・ヘルスケア・高齢社会・母子保健
