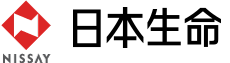社外取締役によるコーポレートガバナンス対談
~コーポレートガバナンスと今後の成長戦略~
当社では、経験・見識に基づき、社外取締役および社外監査役を選任しており、
客観的な視点から経営面への監督や助言を受けることで、当社経営の透明性の確保等に努めています。
ここでは、社外取締役の有馬朗人、牛島信の両氏に、当社コーポレートガバナンスの取り組み、
社外取締役に求められる役割、今後の発展に向けた課題などについて伺いました。
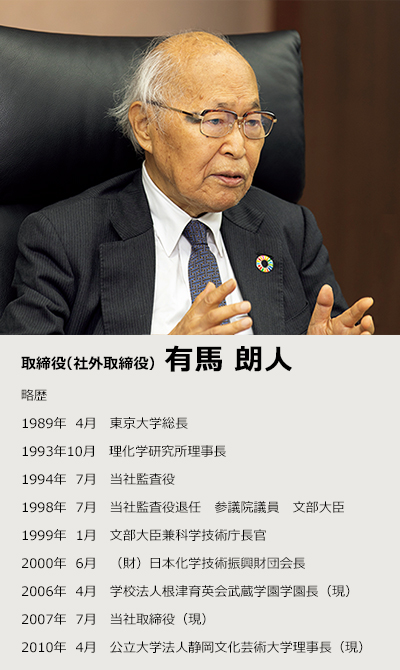
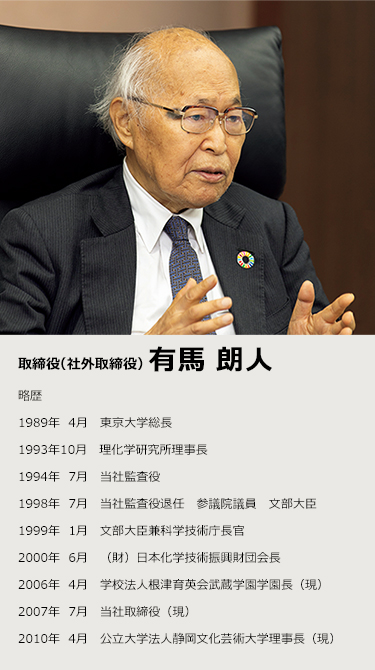
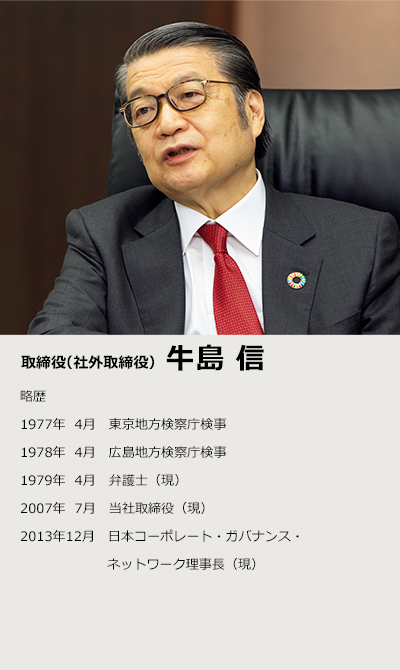
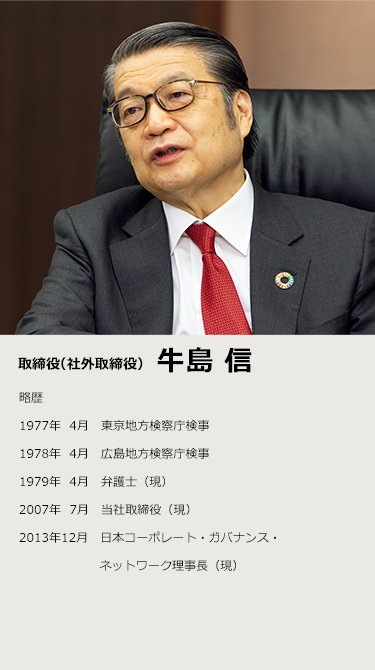
コーポレートガバナンスへの取り組み
当社のコーポレートガバナンスへの取り組みをどのように評価されていますか。
- 牛島
- 社会に役立つ存在であることが会社の本質であり、商品やサービスの提供に加え、特に生きがい、働きがいを伴う雇用の提供が重要であると考えています。コーポレートガバナンスにおいても、会社が社会にとって役立つ存在になっているかという視点を重視しています。また、私は、会社というものは経営者次第であり、社会に役立つ存在となれるかは経営トップの手腕にかかっていると思います。従って、コーポレートガバナンスでは「経営トップの選任」を重視すべきだと見ています。従業員数の多い企業の経営トップをどう選ぶかは、国民的課題と捉えるべきでしょう。
- 有馬
- 私は、外部・第三者の視点を重視します。過去の私の経験からお話ししたいと思います。私が東京大学に奉職していたとき、国立大学のあるべき姿を模索する中で、まずは自分たちで自己評価を実施しました。当時、世間では、国立大学は論文も少なく研究力も乏しいといわれていましたが、自己評価をしてみると、東京大学をはじめ国立大学は、日本の研究機関の中では論文数が多い、けれども、諸外国の大学と比べるとやや少ない、そのような事実が分かりました。
しかし、自己評価だけでは、一人よがりな評価になってしまう恐れがあるため、次に外部の有識者による第三者委員会を立ち上げ、東大物理学教室の実力をはかる取り組みを実施しました。委員には、海外の高名な研究者等、錚々たるメンバーを集めて綿密に評価していただきました。
その結果、当時の学生や教官は世界でもトップレベルである一方で、研究・教育環境が不十分であるという評価が出されました。第三者による評価の導入に対しては一部では反対もありましたが、当時の大学が置かれている状況が客観的に明らかになったことで、国立大学の現状に対する社会や行政の理解が進み、後に大学施設費の増加につながるなど、結果的に大成功だったと考えています。こうした体験に鑑みて、日本生命のコーポレートガバナンスでも、日本生命の役員・職員自身が日本生命についてよく理解していること、そして、外部の視点による点検が不可欠だと思います。その点、私自身1994年に日本生命の社外監査役を拝命しましたが、それ以前から、日本生命では外部の視点を取り入れるのが非常に早く、先駆的でした。これはまさにコーポレートガバナンスの出発点であり、模範的であると考えます。 - 牛島
- 外部の視点の取り入れの重要性については私も同感ですね。また、日本生命は社外役員以外にも、積極的に外部の視点を取り入れており、コーポレートガバナンスがうまく機能していると思います。
加えて、株主の資本力が会社の意思決定の背景にある株式会社と異なり、日本生命は相互会社として総代会制度を採用しており、総代会では、一人ひとりが平等に議決権を有しています。総代会等での議論を拝聴すると、総代の方々におかれても、会社全体そして社会全体を意識したご発言が多いように感じます。 - 有馬
- そのとおりですね。だからこそ、社会的責任を果たすために早い時期から、社外役員などを通じて適切に外部の目を取り入れてきたのだと思います。
当社では、経営戦略としてグループ拡大を推進していますが、グループガバナンスをどのように評価されていますか。
- 牛島
- 長年にわたり国内でグループ経営を行ってきた日本生命は、日本企業のグループガバナンスの在り方を示し得る象徴的な存在だと考えています。一方で、日本企業にとって、海外の子会社をハンドリングすることは困難を伴います。車など実体のあるものづくりの会社ならば、海外の子会社であっても比較的統制しやすく成功例も多いのですが、無形のサービスを提供する保険会社の海外での成功例は多くはありません。現在、日本生命はこの困難な取り組みにチャレンジしています。日本生命は、国内も含め、これまでにない多様性を含んだグループガバナンスを実践しており、苦労も尽きないと思いますが、その意欲的な取り組みと工夫に期待しています。
- 有馬
- 相互会社である日本生命が、国内外でさまざまな会社をグループ化していこうとすると、株式会社をグループ傘下に収めて経営を行っていくことになりますが、これはグループガバナンスの実験的な取り組みになると考えています。今後、相互会社と株式会社という異なる会社形態を、日本生命グループとしてどのように一緒に運営していくかが問われていくと思います。ここでも重要なのはやはり外部の視点だと考えています。
社外取締役の役割
当社において、社外取締役にはどのような役割が求められるとお考えですか。
- 牛島
- 私は、相互会社の社外取締役として、契約者である社員の利益を守ることは必須ですが、それと同時に、業務執行取締役の経営判断をサポートすることを重視しています。業務執行取締役が判断に迷う状況や、外部の意見を取り入れたいと考える状況において、私たち社外取締役が疑問の受け止め役や、客観的な意見の出し手の役割を担い、業務執行取締役に省察を促すことで、より良い経営判断につなげることを目指しています。その最たる例が、2018年にあった経営トップの交代です。私たち社外取締役は、良いトップが会社を牽引するということについて、それぞれの視点から意見を述べることで、お役に立てたのではないかと考えています。
他にも、取締役会で業務執行取締役の方々からも多様な意見を引き出すことにそれぞれが努めています。日本生命の取締役会は、議長の一貫したリーダーシップのもと、社外取締役、社外監査役からの発言等も含めて、適切かつ活発な議論がなされている点でも高く評価できます。 - 有馬
- 社外取締役がそれぞれの専門性、経験を生かして意見を述べることが重要です。私の専門は理論物理学ですが、独自の視点から経営の参考になる意見を出すよう努めてきました。また、私は海外での経験も多いため、諸外国の文化や考え方の特徴を踏まえて、海外戦略について意見を述べるよう心掛けています。
- 牛島
- 近年、コーポレートガバナンス強化の観点から、株式会社に指名・報酬を議論する委員会を設けることが推奨されています。日本生命はさらに先行し、社外取締役を中心に、指名・報酬はもちろんのこと、経営計画や重要な投資案件等、より幅広い議論ができる社外取締役委員会が設置されています。この委員会は、取締役会の諮問機関として極めて優れた機能を発揮しており、有馬取締役のような世界的な学識経験者や、大企業の経営者等、さまざまな経験をお持ちの社外取締役が参加しているため、議論のレベルが非常に高いと感じます。
さらに、社外取締役が率直に意見を出し、業務執行取締役が真摯にそれを受け止めて説明等を行っており、コーポレートガバナンスが機能していると私は考えています。 - 有馬
- 私としては、社外取締役委員会に、牛島取締役をはじめ弁護士の方がいらっしゃることで、法制面を踏まえたしっかりした議論に導いていただけるのは、非常に有難いですね。また同委員会には別分野の大企業経営の経験者が社外取締役として参加しており、それぞれの知識・経験を生かして、専門性の高いアドバイスも行っています。社外取締役は日本生命の業務執行から独立していることから、客観的かつ問題の核心を衝いた、鋭く率直な意見が出てきますね。
今後の発展へ向けて
新型コロナウイルス感染症拡大をはじめ、喫緊の社会的課題がある中で、
当社が今後発展を遂げていくために、どのような取り組みを重視されますか。
- 有馬
- 日本生命が直面する重要課題の一つは、グローバリゼーションです。この点に関して、私は「急ぐな」と助言したいですね。調査を深め、データを蓄積したうえで、きちんと判断をしていただきたい。国内の少子高齢化の影響で、海外に活路を求めるのは道理ですが、諸外国の異なる商慣習、人々の気質などを把握できる人材を確保して情報を収集して判断していくべきだと思います。それからもう一つは、少子高齢化が進む社会で、生命保険をどう多様化していくかということです。高齢者の暮らしやすさも重要なテーマになるでしょう。また、今後も新型コロナウイルスのような難しい感染症が発生するなど、新たな危機が起こり得ます。
- 牛島
- 何ごともスピードが大事だといわれる今の風潮の中で、有馬取締役の「急ぐな」という言葉は、万鈞の重みがあります。これは、正確な情報を集めたうえで精査し、打つべき手を打ちなさいという趣旨だと理解しました。現在進行中のオーストラリア子会社での取り組みは、非常に苦労も多いですが、日本生命にとって非常によい経験になっていくと思います。全ての経験を糧にして着実な施策を講じ、次なる段階に進んでいくことを期待しています。また、高齢化社会への対応に関して、お客様であるご契約者が健康で長生きすることは、保険会社にとっても喜ばしいことであり、国内の成熟した生命保険市場の新たな可能性を拓くものです。新型コロナウイルス感染症拡大によりフェイス・トゥ・フェイスでの営業活動が難しくなったことも大きな環境変化です。今後、営業のかたちをさらに発展させていくことを期待しています。
- 有馬
- 大きな環境変化に直面しておりますが、重要なのはやはり、人です。今後、直面する課題に対して、日本生命の従業員が誇りを持って臨めるようにするためには、人材育成が重要です。これからの日本生命を支える皆さんには今後、長く活躍してもらう必要があります。
近年、世間では入社しても数年で辞めてしまうケースが増えており、企業の従業員を育成する力が衰えていると感じています。育成にあたっては、一人ひとりの従業員に働きがいを感じてもらうことが重要です。 - 牛島
- そうですね。日本生命は社会に与える影響が大きく、生命保険を通じて多くのご契約者の生活を支えています。人材育成にあたっては、どうしてその仕事をしているのか、そしてどれだけ素晴らしい影響を社会に与え得るのかということを、従業員自らが理解できるようにすることが重要です。私は、日本生命で働くことは素晴らしいチャンスであり、日本生命は誇るに足る会社だと思います。日本生命での働きがいを、とりわけ若い方々に理解いただくことが大切ですね。
- 有馬
- 日本生命の役員・職員と接していると、日本生命の一員であることに誇りを持っている方が多いと感じます。加えて、海外展開を進めるにあたっては、それに取り組む人材に、若いうちから海外経験を積ませる必要があります。ぜひ若い方を中心に、オン・ザ・ジョブ・トレーニング等を通じて、日本生命で働くことの誇りを伝えながら、しっかりと人材育成を行ってほしいです。今後も、日本生命の役員・職員の皆さんが、生命保険業に携わることが、自らの人生にとっても非常に重要なこと、名誉なことであると思えるような、人材育成と環境づくりに取り組んでいくことを期待します。