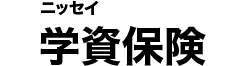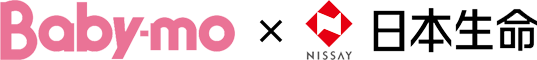
初節句は何をするもの?男の子と女の子、それぞれのお祝いの仕方は?
子育て
2024.11.20

初めて迎える赤ちゃんの「初節句」。いざ準備しようと思っても、実際にどんなことをするのか戸惑ってしまいますよね。そこで今回は、男の子と女の子、それぞれの初節句のお祝いの仕方についてご紹介します。
目次
「節句」とは?どんな意味があるの?

“節句”というと桃の節句と端午の節句しか知らない方も多いかもしれません。でも実は、節句はこの2つだけではありません。日本には季節の草花に彩られたいろいろな『五節句』と呼ばれるものがあります。
人日(じんじつ)=七草の節句
月日:1月7日
植物:七草
行事食:七草粥
上巳(じょうみ/じょうし)=桃の節句(ひな祭り)
月日:3月3日
植物:桃
贈り物:ひな飾り
行事食:草餅、菱餅、ひなあられ、ちらし寿司、はまぐりのお吸い物
端午(たんご)=菖蒲の節句
月日:5月5日
植物:菖蒲
贈り物:鎧兜、甲冑、五月人形、鯉のぼり
行事食:ちまき、柏餅
七夕(たなばた/しちせき)=笹の節句(星祭)
月日:7月7日
植物:笹竹
行事食:そうめん
重陽(ちょうよう)=菊の節句/栗の節句
月日:9月9日
植物:菊
行事食:栗ご飯、菊酒
節句には、それぞれの意味や行事食があります。節句は季節の変わり目を祝う神事のためだけでなく、人々が滋養のあるものを食べて鋭気を養い、周囲との絆を強める貴重な機会でもありました。
女の子の初節句は3月3日の『桃の節句』

女の子の初節句は、生まれて初めて迎える3月3日。かつては旧暦3月上旬の「巳」の日に行っていたことから、正式には『上巳の節句』と言います。また、旧暦3月頃は桃の花が咲く時期なので『桃の節句』とも呼ばれます。
3月3日が五節句のひとつに定められたのは、江戸時代。武家や町人の間で、ひな人形を飾って女の子の成長を祝う、ひな祭りの風習が広まりました。江戸中期になると、女の子が生まれた最初の節句にひな人形を飾るようになり、それが毎年の行事として定着したとされています。
女の子の初節句では何をする?
ひな人形を飾る
女の子の初節句では、ひな人形を飾ります。ひな人形は、2月中旬頃から飾り始め、3月3日が終わると早めに片付けるのが一般的ですが、地域や家庭によって風習が異なるため、その地域や家庭の習慣に合わせます。
はまぐりのお吸い物や、ちらし寿司を食べる
ひな祭りの日には、特別な料理が用意されます。はまぐりのお吸い物やちらし寿司、ひし餅、白酒(お子様の場合は、アルコールが含まれていない米麹が原料の甘酒で代用)などがあります。これらの料理は、子どもの健康や幸運を祈る意味が込められています。
桃などのお花を飾る
ひな祭りには縁起の良い花として、桃の花のほか、菜の花、紅白の梅などが飾られます。
このほか、「つるし雛」や「流し雛」といった地域独特のひな祭りを行っている地域もあります。
男の子の初節句は5月5日の『端午の節句』

男の子の初節句は、生まれて初めて迎える5日5日。『端午の節句』といわれますが、『菖蒲の節句』『あやめの節句』と呼ばれることも。
端午の節句が、現在のように男の子の誕生と成長を祝う日になったのは、江戸時代に入ってからのこと。武家の間だけでなく、広く庶民にも広まり、男の子の健やかでたくましい成長を祈るようになったとされています。
男の子の初節句では何をする?
五月人形を飾る
鎧や兜のほか、金太郎や武者人形といったさまざまな種類の五月人形があります。子どもがたくましく立派に育つようにという願いが込められています。
鯉のぼりを飾る
鯉が滝を昇り竜になるという伝説に由来するもので、子どもの成長や出世を願って飾られるようになりました。
ちまきや柏餅を食べる
災いから身を守ったり、子どもの健康と一家の繁栄を願ったりする意味合いから、端午の節句では、ちまきや柏餅を食べることが一般的な習わしです。
菖蒲湯に入る
邪気を払う力があるとされている菖蒲。子どもの無病息災を願って菖蒲湯に入るのが習わしになっています。
ひな祭りと同様に、端午の節句でも地域特有の風習や違いがあります。例えば、五月人形は関西で鎧飾り、関東では兜飾りが多いと言われています。
初節句でお祝いをもらったらお返しは必要?

子どもの初節句でお祝いをいただくこともあるでしょう。お返ししたほうがよいか迷うところですが、初節句のお祝いの席に参加された親戚や祖父母からお祝いをいただいた場合は、内祝い(うちいわい)を贈らないことが一般的です。親しい身内が集まり、子どもを囲んで楽しく過ごすお祝いの席そのものが内祝いとなるからです。
お祝いの席に来られない方には、「内祝い」として子どもの名前でお返しをします。御礼の手紙や子どもの写真を添えてあげると喜ばれますよ。
監修者プロフィール
本間美加子さん
早稲田大学教育学部卒業後、編集プロダクション勤務を経てフリーライターに。和の伝統、日本文化を中心に執筆中。おもな著書に『神社の解剖図鑑2』(エクスナレッジ)『日本の365日を愛おしむ-季節を感じる暮らしの暦-』(飛鳥新社)『ふくもの暦』(マイクロフィッシュ)『暮らしの図鑑 幸せを招く縁起物』(翔泳社)など。