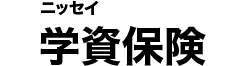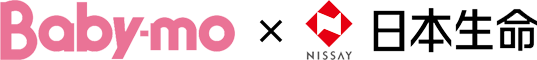
冬に気をつけたい【赤ちゃんがかかりやすい3大感染症】とは?
予防法と自宅ケアをチェック
子育て
2024.11.20

インフルエンザやウイルス性胃腸炎などの感染症は、寒くなるにつれて流行のピークを迎えます。赤ちゃんを感染症から守るための予防法と、かかってしまった場合のケアについて、小児科医の先生に教えてもらいました。
赤ちゃんがとくに気をつけたい「3大うつる病気」

ここでは、冬に流行する感染症のなかで、赤ちゃんがとくに気を付けておきたい病気を3つご紹介します。
1インフルエンザ
どんな病気?
インフルエンザウイルスに感染することでかかる病気。毎年冬~春にかけて流行し、非常に感染力が強いのが特徴。また、毎年流行するウイルスの種類が変わるため、何度もかかる可能性も。
症状は?
初期症状はせきや鼻水などかぜと似ていますが、頭痛や関節痛、筋肉痛など全身症状が強く出ます。また、急に高熱が出たり、一度下がって熱が上がったりすることも。抵抗力が弱い赤ちゃんは、重症化、合併症に注意。
治療とケアは?
インフルエンザと診断されたら、指定された期間は自宅安静を。熱がある間はこまめな水分補給をしましょう。抗ウイルス薬の「タミフル」は、1歳未満の赤ちゃんでも使えますが、通常は自然に治る病気です。治療については、かかりつけ医とよく相談を。
2ウイルス性胃腸炎
どんな病気?
ウイルスに感染して起こる急性の胃腸炎で「おなかのかぜ」と呼ばれることも。冬にかかりやすく、初秋から春先にはノロウイルス、冬から春先にはロタウイルスも流行。どちらも感染力が高く、家庭内感染に注意。
症状は?
急激な嘔吐や下痢、発熱からスタート。うんちは水っぽく、1日10回以上出ることも。ノロウイルスが原因の場合、ひどい嘔吐や下痢は1~2日で落ち着きますが、ロタウイルスの場合、白っぽい便が出たり、頻回の下痢が1週間続いたりする場合も。
治療とケアは?
嘔吐のピークは症状が出始めて数時間~半日。嘔吐や下痢は、病原体を体の外に出そうとする防御反応です。下痢の場合、薬で無理に止めるのではなく、整腸薬などで対症療法を行います。
ただし、嘔吐や下痢が止まらず水分補給ができない場合は早めに受診を。赤ちゃんは脱水を起こしやすく、ほかの病気の可能性も。
3RSウイルス感染症
どんな病気?
RSウイルスが原因の呼吸器の感染症。ウイルスを持っている人のせきやくしゃみ、ウイルスが付着しているものにさわることで感染。生後1歳までに約半数、2歳までにはほぼ100%の子が一度は感染します。以前は冬の感染症と言われていましたが、近年は寒くない季節にも流行が見られます。
症状は?
ウイルスに感染してから、4~6日の潜伏期間ののち、鼻水やせきが数日続きます。年長児では軽いかぜ症状ですむことが少なくありませんが、はじめて感染した赤ちゃんの3割は細気管支炎や肺炎などを引き起こす場合も。
治療とケアは?
ウイルスに特効薬はないので、症状をやわらげる対症療法が基本。鼻水やせきなど、かぜの症状程度であれば、受診したうえで安静に過ごしましょう。せきがひどくなる、呼吸がゼロゼロするなど呼吸状態が悪くなったときは、すぐに病院へ。月齢が低いほど急激に悪化しやすいので注意を。
赤ちゃんが感染症にならないための予防法は?

ウイルスを体に入れない!外から帰ったら必ず手洗い
手についたウイルスは、手洗いが効果的。流水で洗うことで、効果的にウイルスを落とせます。石けんを泡立て、泡でやさしく赤ちゃんの手を包みながら洗ってあげましょう。
うがいができない赤ちゃんは水分補給をこまめに
水を飲むと、のどにいるウイルスは胃に流れ落ちます。気道粘膜から感染するインフルエンザウイルスは胃液の中では活動できないので、ある程度は予防効果があります。
ただし、胃腸炎ウイルスのように腸から感染するものもあるので、予防効果は限定的です。
よく食べてよく眠り、免疫力をアップ!
病原体が体に入ってきても、それとたたかって排除するのが免疫システムです。赤ちゃんが自分の力で病気を乗り越えていくために、生活習慣から免疫力を高めたいもの。
たっぷりの睡眠と栄養バランスのいい食事をとるように心がけましょう。また、スキンケアで肌のうるおいを保つことも、全身の免疫力を高めるといわれています。
人混みの中にはなるべく出かけない
いちばんの予防法は、かぜやインフルエンザの原因になるウイルスをもらわないこと。流行シーズンは、なるべく人混みへ出かけないよう心がけましょう。
赤ちゃんは重症化することも。サインを見逃さないで

インフルエンザなどのウイルスは、寒くて乾燥した冬に活発になります。大人もかかりやすくなりますが、免疫機能が未熟な赤ちゃんの場合は重症化しやすいため、注意が必要です。
でも、もし感染症にかかってしまったとしても、心配しすぎないで。適切な受診とケアをしてあげれば、乗り越えていけるはずです。パパやママが赤ちゃんの様子をよく見て「いつもと違う」「おかしいな」と気づけるようにしておきたいものですね。
監修者プロフィール
総合母子保健センター 愛育クリニック
院長 渋谷紀子先生
東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院、山王病院、NTT東日本関東病院などの勤務を経て、現職。日本小児科学会専門医・認定指導医。日本アレルギー学会専門医。監修に『はじめてママ&パパの0~6才病気とホームケア』(主婦の友社)など。