第66回 消費税率10%時に軽減税率が導入されるか?軽減税率ってどういうもの?
3分でわかる 新社会人のための経済学コラム2015年8月1日
低所得者に配慮した政策
2017年4月、消費税率は10%に引上げられる予定です。消費税は、誰もが買い物といった消費活動を行うので、国民全体で広く薄く負担できるというメリットがあります。一方で、消費税率は、低所得者ほど所得のうち消費に回す割合が高いため、高所得者よりも所得に対する税負担率が大きくなるという「逆進性」の問題が生じます。 そのため、政府は消費税率を10%に引上げるにあたり、低所得者の負担軽減策として「軽減税率」と「給付付き税額控除」という案を検討していました。
「軽減税率」とは、標準的な税率(2017年4月以降の消費税の場合10%)とは別に低い税率を設けることです。生活必需品である食料品などを低い税率(軽減税率)にすることで低所得者の負担を和らげることができます(図表1)。「給付付き税額控除」とは、一定の所得より低い人を対象に所得税を減らすことや、給付金を支給する制度のことです(図表2)。現在、政府は「軽減税率」の導入に向けた話合いを進めています(※1)。
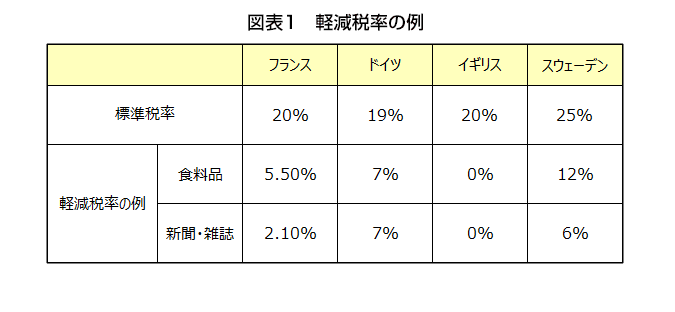
(注)2015年1月時点
(資料)財務省HPより作成
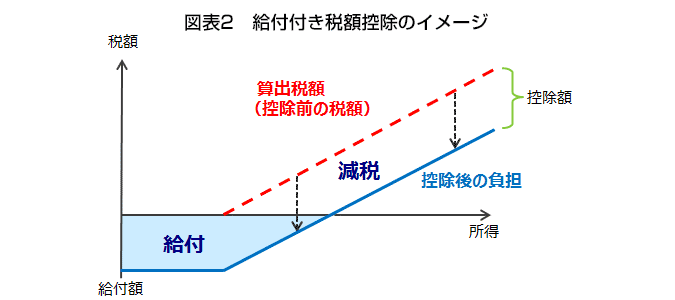
(資料)ニッセイ基礎研究所作成
軽減税率の問題点
諸外国では欧州諸国を中心に多くの国が、付加価値税率(日本でいう、消費税)の軽減税率を食料品や新聞・雑誌といった品目に導入しています。ただし、既に導入している国の経験からいくつかの問題点が指摘されています。
軽減税率を導入すると、8%や10%といったように複数の税率が存在することになります。標準税率で販売した商品を軽減税率の商品として販売したことにするなど、税額を低く申告する脱税行為が生じかねません。このため、政府は脱税行為をチェックするため、企業側に品目ごとに税率・税額を記載する書類を残すことを義務付ける必要が生じます。結果、企業に追加のシステム対応といった納税事務負担が増すことになります。
どの商品に軽減税率を適用するかという線引きの難しさもあります。例えば、フランスでは贅沢品のキャビアは標準税率ですが、同じ贅沢品のフォアグラとトリュフは国内産業保護の観点から軽減税率が適用されています(図表3)。このように線引きが難しいだけでなく、政治的な判断で特定分野が優遇されるなど、社会的不公平感が拡大する恐れがあります。現在日本は、主に食料品への軽減税率導入が検討されていますが、食料品以外の品目に広がる可能性もあります。実際、諸外国では、新聞や医薬品といった食料品以外のものにも幅広く適用されています。
このように「企業の納税事務負担の増大」や「対象品目の線引きの難しさ」といった問題が生じるため、給付付き税額控除の導入を再検討すべきという意見があがっています(※2)。
さらに、日本においては財源の問題もあります。そもそも、消費税率を5%から10%に引上げる目的は、少子化対策などの社会保障の充実や将来世代への財政負担のつけまわしを軽減することです。軽減税率を適用する品目が拡大すればするほど、消費税率の引上げで予定していた税収増分が少なくなります。
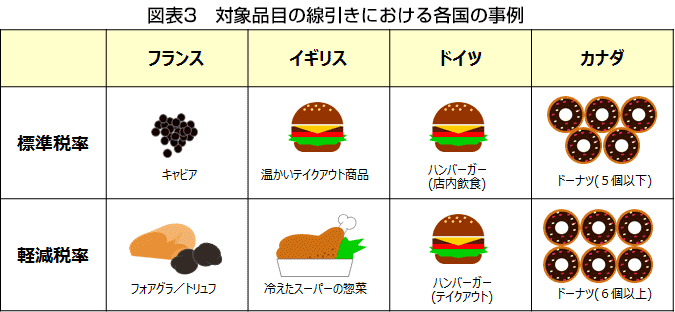
(資料)社会保障改革に関する集中検討会議(第九回)(資料3-7)より作成(※3)
国民からの支持は高い

軽減税率は、国民からは高い支持を得ています。最近の世論調査(※4)では、軽減税率の導入に賛成する人が8割を超えている状況です。「食料品をはじめとする生活必需品が安くなる」など、多くの国民が負担軽減を実感できるからでしょう(※5)。政府が軽減税率の導入を目指すのは、こうした高い支持が得られていることも大きいでしょう。
現在、政府は軽減税率の具体化に向けて、「①酒を除く飲食料品」、「②生鮮食品」、「③精米のみ」という3つの案を軸に話合いをすすめています(図表4)。2017年4月導入を目指す政府は、今秋までに基本的な方針を示す予定です。今後の話合いの行方に注目です。
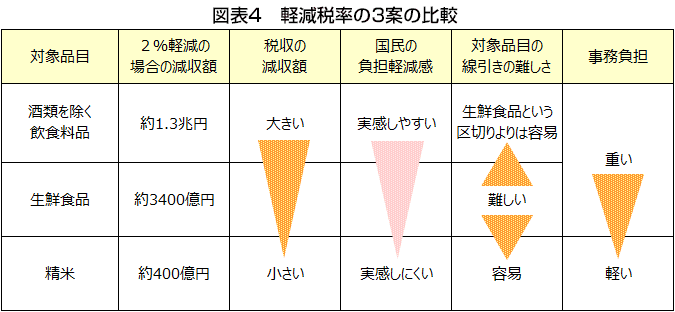
(資料)第3回消費税軽減税率制度委員会(与党税制協議会)資料より作成
(注:本コラムは、筆者の個人的見解に基づいて書かれています。)
-
(※1)平成27年度与党税制改正大綱では「消費税の軽減税率制度については、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める」と明記されている。
-
(※2)給付付き税額控除は、所得などの正確な情報を確実かつ即座に把握できるといった執行上の基盤を整える必要があることが導入に向けた課題とされている。しかし、運用開始予定のマイナンバー制度を活用することで、こうした実施体制の整備が容易になるとの意見も多い。また、諸外国では、米、英、独、仏、オランダ、カナダ、ニュージーランド等が給付付き税額控除を導入している。
-
(※3)斉藤誠「消費増税の低所得者対策〜軽減税率と給付付き税額控除〜2014-02-28」を参考としている。
また本コラム執筆にあたり、内容も参考にしている。 -
(※4)産経新聞・FNN世論調査2014年10月実施結果によれば、生活必需品の消費税率を抑える軽減税率に関しては83.9%が「導入すべきだ」と回答している。
-
(※5)軽減税率は、低所得者だけでなく全ての消費者に恩恵が及ぶため、対象品目によっては高所得者ほど恩恵をうけるということも起こりうる。そのため、軽減税率は、消費税の「逆進性」対策として望ましくないとの意見もある。
(ニッセイ基礎研究所 薮内 哲)
