第95回 6組に1組!?不妊に悩む夫婦の割合
3分でわかる 新社会人のための経済学コラム2018年1月4日
不妊に悩んでいる夫婦は6組に1組?

国立社会保障・人口問題研究所が実施した「第15回出生動向調査(2015年)」によれば、妻の年齢が50歳未満で、結婚後15〜19年の夫婦のうち、過去に不妊の心配をしたことがある割合は29.3%と全体の3割近くにのぼり、増加傾向にあります。その半分以上にあたる約15.6%の夫婦が治療を受けていることから、「夫婦の6組に1組が不妊(※1)に悩んでいる」と言われることがあります。
「不妊」増加の背景として、ライフスタイルの変化や女性の社会進出等にともなう晩婚化があげられます。医療技術が進歩し、寿命が長くなった今日においても、出産に適した年齢は昔と変わっておらず、加齢によって子どもを授かりにくくなると言われています。(※2)
しかし、最近では高齢であったり、疾病を抱えていても「不妊治療」を受けることで子どもを授かる可能性が出てきました。国でも不妊治療のうち、保険適用外の費用が高い体外受精に対して補助を行う制度ができるなど、治療を後押しする動きがあります。
- (※1)日本産科婦人科学会によると、「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間(1年が一般的)妊娠しないことを言います。(日本産科婦人科学会ホームページhttps://www.jsog.or.jp/public/knowledge/funin.html
より)
- (※2)日本産科婦人科学会ホームページ等より
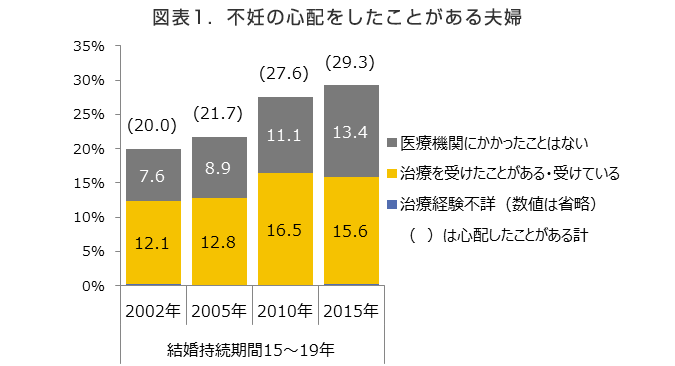
(出典)国立社会保障・人口問題研究所「出生動向調査(各年)」
それでも、治療に対する不安は強いと思われます。そこで、ニッセイ基礎研究所が2015年に行ったアンケートの結果を使って、どの程度の人が治療を検討しているのか、その際どういった不安があるのかを見ていきたいと思います。
「積極的に治療を検討」は2割程度
不妊は、女性だけの問題ではなく、なんらかの形で男性側にも原因がある場合が3分の1から半分近くに及ぶと言われています。(※3)しかし、ここでは、不妊治療により関心が高いと思われる、出産を希望する20〜44歳の女性を対象としたアンケートの結果を示します。
まず、妊孕力(にんようりょく)の検査を受けている夫婦がどの程度いるか見てみます。妊孕力とは、子どもを産む力のことで、女性は卵巣予備能(残っている卵の数の目安)等、男性は精子の濃度や運動率等について検査ができます。検査実施率は、子どもがいない既婚女性でもっとも高く18.5%でした。さらに23.0%が今後の検査をする意向があります。子どもがいない夫婦では男性も検査実施率が高く、16.9%が検査を受けています。未婚者では実施率はまだ低いですが、今後の意向は高くなっています。
- (※3)ニッセイ基礎研究所編「みんなに知ってほしい不妊治療と医療保障」(保険毎日新聞社)第1章
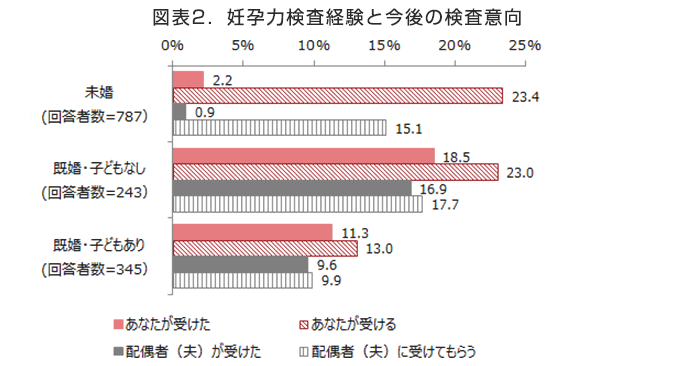
(資料)ニッセイ基礎研究所「2015年生命保険会社に期待するサービスに関する調査」
続いて、思うように子どもができなかった場合、不妊治療を検討するかを尋ねると、「検討しない」と回答した人は15%程度にとどまり、残る85%は何らかの形で「検討する」と回答しています。配偶者と相談したうえで検討する女性が多いですが、「積極的に検討する」と回答した割合も2割程度となっています。特に、子どもを持たない既婚女性の回答は「積極的に検討する」が27.6%と高く、治療への関心の高さがうかがえます。
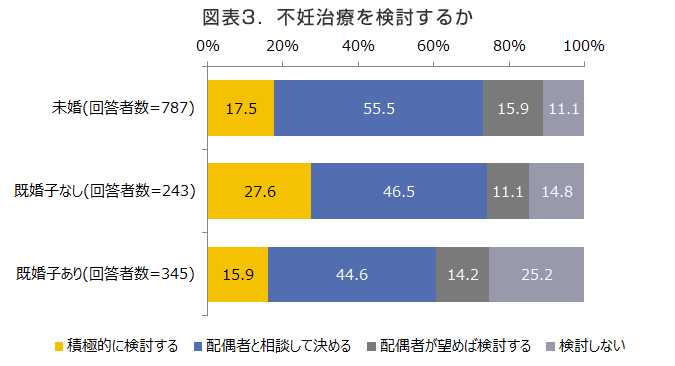
(資料)ニッセイ基礎研究所「2015年生命保険会社に期待するサービスに関する調査」
不妊治療を受けることになった場合の不安や不満を尋ねると、7割以上が「治療費が高いこと」と回答しており、他項目と比べて突出して高くなっています。次いで「精神的な疲労」が5割程度、「長期間にわたって通院すること」「肉体的な疲労」が4割を超えて続きます。
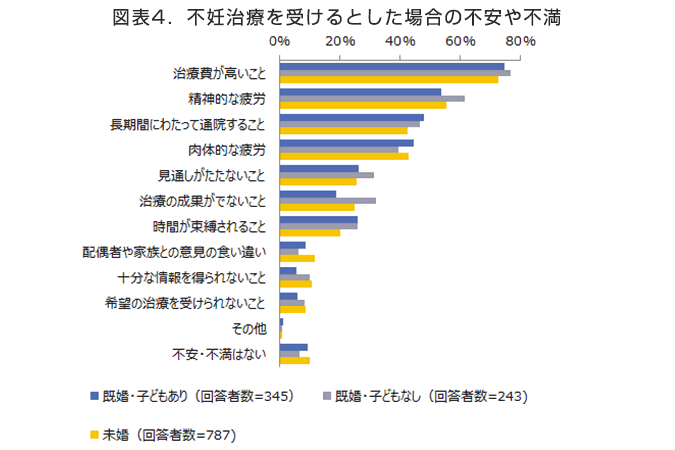
(資料)ニッセイ基礎研究所「2015年生命保険会社に期待するサービスに関する調査」
妊孕力の検査や不妊治療の検討は、今後出産を考えている女性にとって一般的となってきていると言えるでしょう。しかし、不妊治療が一般的になりつつあるとは言え、費用面や精神面での不安が大きい様子がうかがえます。
費用面での不安解消のためには国や企業による補助制度等の充実が期待されます。同時に、精神的・肉体的な疲労を少しでも軽減し、長期間の通院もできるように家庭や勤務先でのサポートする体制が重要でしょう。
(ニッセイ基礎研究所 村松 容子)
筆者紹介

