第93回 2012年11月を底に緩やかな景気回復が続く日本。 戦後2番目の長さ(57カ月)の「いざなぎ景気」越え!?
3分でわかる 新社会人のための経済学コラム2017年11月1日
景気の波とは
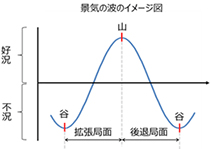
景気には、良くなったり悪くなったりを繰返す波があり、良くなっている時を「拡張(回復)局面」、悪くなっている時を「後退局面」と言います。(※1)
そして、経済活動が最も活発な所を「山」、最も低迷している所を「谷」と言います。
現在の日本経済は、2012年11月を「谷」として景気回復が続いています。その長さは2017年9月で58カ月となり、戦後2番目の長さである「いざなぎ景気」の57カ月(1965年11月~1970年7月)を超えた可能性が高いと言われています。(※2)
- (※1)以下の文章では、分かりやすさを重視して「拡張」ではなく、「回復」という言葉を使います。
- (※2)景気の転換点である「山」や「谷」がいつだったかは、内閣府経済社会総合研究所が定めており、データの蓄積を待って数年過ぎてから判断されています。
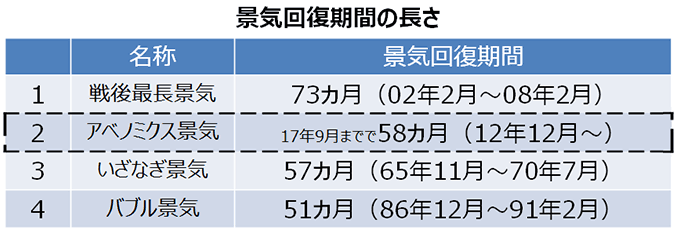
(注)名称はメディア等で用いられたもので、正式名称ではない。
(資料)内閣府資料等より作成
雇用環境、企業収益は着実に改善
過去の景気回復局面と比較して、現在の景気回復のパターンを見ていきましょう。まず、雇用情勢は着実に改善しており、新社会人のみなさんも就職活動を通じてそのことを実感したかもしれません。雇用者数の増加人数を比べると、バブル期の勢いには届かないとしても、2002年2月から始まった戦後最長景気を上回るペースで雇用者数は増加しています。生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少していますが、高齢者や女性を中心に労働市場への参入が進んでいるためです。
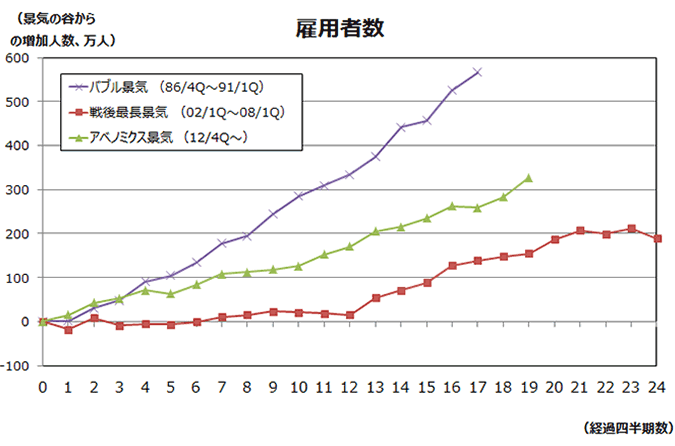
(注)季節調整値。アベノミクス景気の19四半期目は7,8月の平均
(資料)総務省「労働力調査」
次に、企業収益も好調です。経常利益は、中国経済の減速懸念から円高が進み、2015年後半から2016年前半にかけて悪化する局面もありましたが、その後は再び急回復し、バブル景気を上回りました。経常利益(季節調整値)は2017年4-6月期まで3四半期連続で過去最高の水準を更新しています。
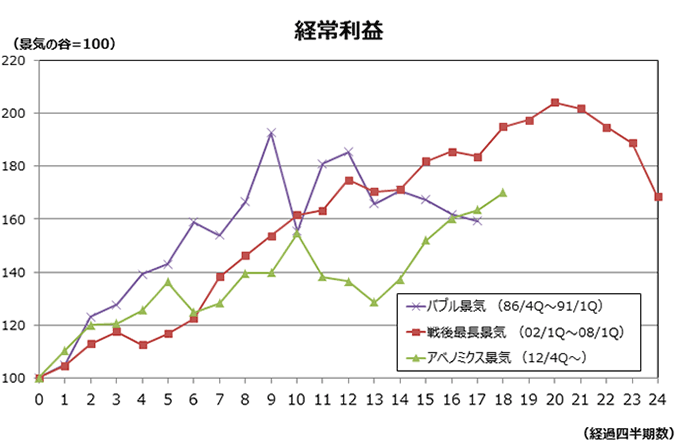
(注)季節調整値
(資料)財務省「法人企業統計」
実感がないのはなぜ?
回復局面が長期間続いているのに、実感がないと言われるのはなぜでしょうか。その理由として、実質賃金 (※3)の低迷が挙げられます。パート・アルバイトの時給は上昇しており、政府の要請を受けて経済界でも賃上げの動きが広がっていて、名目賃金は緩やかに上昇していますが、一方で物価も上昇しており、実質的に購買力は低下しています。
そのため、個人消費の回復がもたついています。個人消費は、消費税増税後は大きく落込んだ後、持直しのペースは緩やかな状態が続き、ようやく駈込み需要前の水準まで回復してきました。個人消費の水準は、景気回復が始まった時からほとんど変わっていないと言えます。
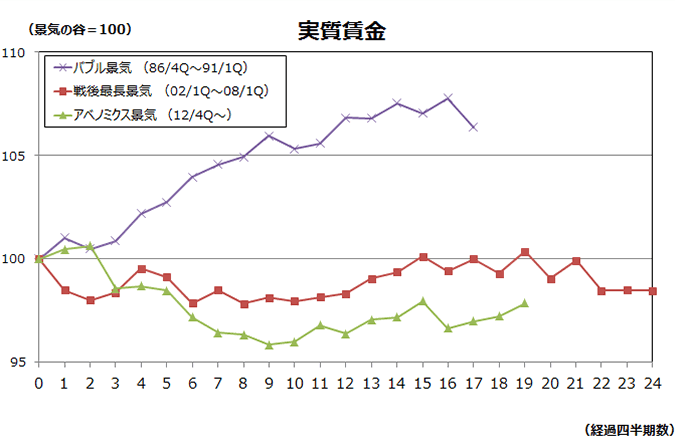
(注)季節調整済の現金給与総額、事業所規模30人以上の常用労働者アベノミクス景気の19四半期目は7,8月の平均
(資料)厚生労働省「毎月勤労統計」
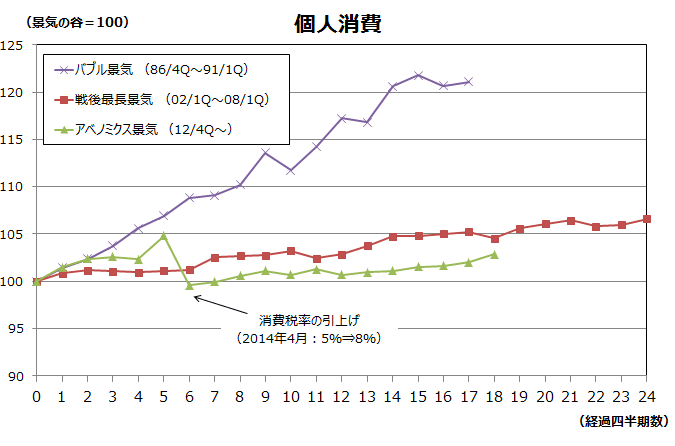
(注)実質季節調整系列
(資料)内閣府「四半期別GDP速報」

海外経済も日本と同様に回復が続いており、今のところ、景気が後退する可能性は低そうです。このまま、2019年1月まで景気回復が続けば、戦後で最も長い景気回復になります。
今後は、実感を伴ったものとするためにも、家計部門まで景気回復の恩恵が行渡り、経済の好循環を実現することが望まれます。
- (※3)実質賃金については、当コラムの第59回「給与明細の数字はプラス!なのに実質賃金はマイナス2.8%??(2014年10月)」
https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/kako/59.htmlを参照ください。
(ニッセイ基礎研究所 白波瀨 康雄)
