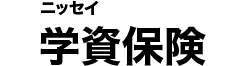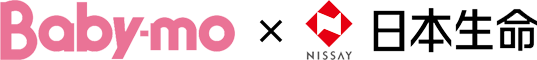
保活はいつから始める?
保育園入園に向けて、時期別にやっておくことリスト
子育て
2024.05.13

職場復帰を予定しているなら、避けて通れないのが「保活」です。聞いたことはあるものの、「いつから何をすればいいの?」と不安に思っている人も多いはず。今回は4月入園を目指した保活のスケジュールや保育園の選び方、実際に保活を経験した先輩ファミリーの体験談などを紹介します。また、保活のエキスパート・普光院亜紀さんに最近の保活事情についてお話も伺いました。
- ※(注)調査の概要:2024年2月に実施。育児誌『Baby-mo』公式インスタグラム(ストーリーズ)でのアンケート、およびBaby-mo編集部による対面調査。
目次
保活はいつからスタートすればいい?
保活のスタートは早ければ早いほどよいと言っても過言ではありません。どんな園があるのかを調べたり、園の見学をしたり、申請書類を作成したりなど、やるべきことが多いからです。余裕を持ったスケジュールを立て、早め早めに行動しましょう。
保活のスケジュールは?

STEP1:情報収集(4~8月ごろ)
まずは住んでいる自治体のホームページで保育園情報を入手します。入園案内の資料をダウンロードし、申し込みの流れや通えそうな園などをチェック。わからない点は、自治体の担当窓口に相談しましょう。また、近所のパパママ友の口コミも貴重な情報源。ぜひ機会があればリアルな声を聞いてみて。
<先輩ファミリーの体験談>
- ・4月からリサーチ開始。役所には早めに行き、できるだけこまかく説明してもらいました。ネットで口コミもチェック!(東京都/いーくんママさん)
- ・締め切りの1カ月前ギリギリに始め、見学に行けなかった園はネットでレビューや教育方針を読みました。(東京都/Pさん)
4月から時間をかけた人も多い一方で、 10 月から始めたギリギリ派も。「生後3カ月のときに締め切りだったので情報収集できなかった」という声もありました。
STEP2:園見学・リサーチ(5~9月ごろ)
情報収集と並行して、気になる保育園があれば、見学へ行きましょう。申し込みは保育園に直接電話をするのが一般的。見学の際は、保育の様子や施設の環境などをしっかりチェックして。聞きたいことをまとめておくこともおすすめです。
<先輩ファミリーの体験談>
- ・荷物は園によって差が大きいです。毎日のことなので、荷物が少ないと楽ちん。なので、園見学では荷物について質問しましょう!(千葉県/Aさん)
- ・行ける範囲はすべて見学しました! 幼稚園で延長あり(定額)など、知っていると選択肢を増やせます。ママ友、ふだん行く美容院やカフェで働くママさんの生の声が有益でした。(神奈川県/えりこさん)
Qいくつの園を見学した?
- 1位……3園
- 2位……6園
- 3位……2園
2~6園という人が多数。最も多かった人は「15園」でした。「きょうだいがいるから」という理由で見学をしなかったという人もいました。
STEP3:申請書に記入(9~10月ごろ)
自治体によって違いはありますが、申請書は役所や保育園に置いてあります。申請書だけでなく、復職予定の職場に記入してもらう書類などもあるので、余裕を持った行動を心がけて。自由記述欄がある場合は、生計面や仕事の状況など保育を利用できないと困る事情を補足するのもよいでしょう。
<先輩ファミリーの体験談>
- ・会社に記入してもらう必要書類に、思った以上に時間がかかりました。余裕を持って進めていたので焦らずにすみました。(大阪府/N.Sさん)
- ・夫婦ともにフリーランスなのですが、自宅外で仕事をしています。それを証明する書類や仕事の実態がわかるものが必要で、少々手間がかかりました。(愛知県/Y.Tさん)
Q申請書にいくつの園を記入した?
- 1位……3園
- 2位……1園
- 3位……5園
記入数に制限がある場合や欄外にも記載できるなど、地域によって差があります。「自宅が駅付近のため、小さい園がたくさんあって10園以上申し込んだ」という人も!
STEP4:申請書を提出(10~12月前半ごろ)
必要書類がそろったら、申し込みます。役所の窓口に持参、郵送、オンライン申請など、申し込み方法や提出期限は各自治体によって異なるため、必ずチェックを。また、書類に不備があった場合は再提出になる可能性が高いので、余裕を持って提出するようにしましょう。
<先輩ファミリーの体験談>
- ・早生まれのため、4月入園は叶わなかったのですが、自治体のホームページをこまめにチェックしていたら、6月に希望園で2枠の空きが! 生後4カ月で入園できました。(東京都/いろママさん)
- ・申請書には1園のみ記入。住んでいる自治体は0歳児の空きが少なく、1歳児の枠が多い。長男が通っていた、自宅近くの保育園に4月入園が決まりました。(埼玉県/あおママさん)
Q入園した園は第何希望だった?
- 1位……第1希望
- 2位……二次募集・入れなかった
- 3位……第2希望
半数以上の人が第1希望に入れた一方で、約2割は二次募集や入れなかったという結果に。第1希望に入れた人は「きょうだいポイントのおかげ」との声多し。
STEP5:入園決定(1月後半~2月ごろ)
役所から各家庭に入園可否の選考結果が通知されます。選考に通った場合は、入園に向けて準備を進めていきましょう。
STEP6:入園(4月)
入園してしばらくは「慣らし保育」からスタートします。預かり時間が短いこともあるので、スケジュールをきちんと確認しましょう。
もし決まらなかった場合は?
もし希望するすべての園に入れなかった場合は、二次募集や認可外保育園などにすぐ応募を。認可外保育園にも定員はあるので、合否の結果が出てから動き出すのではなく、今から情報収集や見学をしておくことをおすすめします。
保活のエキスパート・普光院亜紀さんに聞きました!
保育園入園のために知っておきたいことQ&A

Q1 保育園の入園事情は地域差が大きいと聞きますが、本当でしょうか?
「全国的に待機児童数が減少し、保育園に入りやすくなってきました。ただし、国や自治体が発表する待機児童数は、認可に落ちて認可外を利用している子どもの数が差し引かれているなど、実態と合わないところもあり、『待機児童数ゼロ』をうたう自治体でも希望者全員が認可園に入れているわけではないことに注意が必要です。実際の入園しやすさは地域、時期、年齢クラスによって違いがあります。首都圏では、都心通勤圏の便利な駅周辺や、若い世帯向けの住宅建設が進められている地域などで、入園事情が厳しくなりがちです。一方、地方では少子化が進み、保育園の空きが埋まらないという悩みを抱える地域もあります」(普光院さん)
Q2 やはり0歳児の4月入園が入りやすいのでしょうか?
「保育園も全クラスが4月に進級します。ほとんどの子どもが1歳児クラスに進級する0歳児クラスは、ほぼクラス定員分の人数が募集されますが、1歳児クラス以上は、定員から進級児を引いた人数しか募集されません。特に1歳児クラスは入園希望が多いため、他の年齢クラスよりも競争率が高くなりがちです。ただし、0歳児クラスと1歳児クラスの定員の差が大きい園や、0歳児クラスがない園は、1歳児の募集人数が多くなるので、少しは入りやすいかもしれません」(普光院さん)
Q3 認可保育園の入園選考について教えてください!
「認可の保育施設(認可保育園、認定こども園、小規模保育、家庭的保育など)は、保護者が働いているなど『保育の必要性』を認められる子どもが入園できます。入園申し込みは自治体で受け付け、クラスの定員を超える申し込みがあった場合には、入園選考(利用調整)が行われます。その基準として『保育の必要性』の度合いを点数化する指数が決められていて、指数が高い家庭が優先されます。指数には勤務時間などで判定される基準指数のほか、ひとり親、認可外保育施設を利用している、きょうだいが在園している園を希望している、などの家庭や子どもの状況に応じて加点する調整指数があります。子どもを見られる祖父母との同居は減点になる場合もあります」(普光院さん)
必読! 最近の保活事情や育休中の注意点、園の空き状況の調べ方

近年の保活事情の変化としては、大きく次の2つがあります。
- ①子どもの数が減って、全体的には競争率が低下中。
- ②育児休業延長制度の利用が増えて、希望が1歳児クラスに集中する傾向。
保育園を考える親の会が調査している「100都市保育力充実度チェック」では、首都圏や政令市の入園決定率(入園を申し込んだ子どものうち入園できた子どもの割合)を調べています。たとえば2023年度を見ると、80.8 %まで上昇していることがわかりました(10年前の2013年度は68.9%)。入園申込者のうち8割程度は認可の保育施設に入園できているということです。ただし、その状況は、数年前と少し変化してきています。
背景には②の育休延長希望者の増加があります。
育休をとれる期間は原則1歳の誕生日の前日までとされています。たとえば6月生まれのお子さんの場合、0歳の4月で生後9カ月、次の4月では1歳9カ月になってしまうので、以前であれば0歳の4月での入園を希望していました。ところが、ここ数年で最大2歳まで育児休業給付金を受けながら育休を延長できる育休延長制度が普及し、1歳を超えて育休をとる保護者が増えています。この結果、保活激戦区だった自治体でも、年度前半は認可保育園等の0歳児クラスに空きが目立つようになってきたのです。その分、1歳児クラスに希望が集中している可能性もあり、園によっては1歳児クラスの入園事情が悪化している場合もあります。
こういった事情も、地域や園によってかなり違いがありますので、自分が希望する園について、早めに情報を得ておくことが重要になります。入園はまだ先と考えているかたも、現時点での自治体の「保育園等の利用案内(入園のしおり)」を取り寄せ、入園候補の園について、自治体が公表している空き状況を調べたり、窓口で4月入園の状況(入園できた家庭の最低指数など)を聞いたりするとよいでしょう。
育休中のかたの注意点
育休延長制度を利用するのかどうかは、親子の健康状態、業務の都合などから判断することになると思いますが、そこに園の入園事情も含めておきましょう。延長後の4月の入園で大丈夫かどうか、特に希望する園がある場合には、入りやすいときに入っておくという考え方が必要な場合もあります。また、育休延長手続には、制度上、認可に入園できなかった証拠(入所不承諾通知)が必要になります。1歳になる月、1歳半になる月に入園申請をするのを忘れないよう気をつけてください。なお、入園申請にあたっては「利用調整において最低点で評価する」などのチェック欄を設けている自治体もありますが、そこにチェックした場合でも、空きがある園には入園内定するので、その点は了解しておく必要があります。
再就職希望のかたの注意点
再就職希望(求職中として入園申請)のかたは、入園選考での指数が低いため、入園をあきらめてきたかたもいるかもしれません。そんなかたも、空き状況情報に注目してください。4月に0歳児クラスが満員にならなかった園では、指数が低い家庭も0歳児クラスには入れたということです。空きがあるクラスには、最低点でも入れるのです。子どもの数の減少により、3歳児クラスなども空きがある園があります。保育園事情がゆるんできたことで、再就職などのキャリアプランも立てやすくなっていると言えます。
空き状況の調べ方
「○○市 保育園 空き状況」などのワードで検索をすると出てきます。空き状況を公表していない自治体もありますが、その場合は、窓口で聞いてみましょう。特に、5月の空き状況は重要です。5月に空きがある園・クラスは、4月はおおむね全員入園できていたと考えられます。
保育の質にこだわって!
子どもは入園すると1日8〜10時間前後を園で過ごします。信頼できる施設長や保育士であるかどうかを、園見学で確認してください。利便性や習い事などよりも保育の質が重要です。園見学については、保育園を考える親の会(*)のウェブサイトもご参照ください。
- *「保育園を考える親の会」https://hoikuoyanokai.com/guide/nursery-visit/
監修者プロフィール
保育園を考える親の会 顧問
普光院亜紀(ふこういん・あき)さん
保育園に子どもを預けて働く親のネットワーク「保育園を考える親の会」顧問・アドバイザー。保育ジャーナリスト。著書に『後悔しない保育園・こども園の選び方』(ひとなる書房)ほか多数。