第131回 日本の行政手続オンライン利用率は7.3%、30カ国中で最下位
3分でわかる 新社会人のための経済学コラム2021年1月6日
日本の行政のデジタル化の遅れ

OECD(経済協力開発機構)の調査によると、2018年時点で日本の行政手続のオンライン利用率は7.3%にとどまっています。これは調査に参加した30カ国の中で第30位、つまり最下位です。【図表1】
内閣府は、日本の行政のデジタル化の課題として、①日本全体でデジタル化を担う人材が不足していること、②人材の勤務先がIT関連産業に偏っており、行政などの公的部門で働く人材が少ないこと、などを指摘しています(※1)。
-
(※1)内閣府「令和2年度年次経済財政報告」(令和2年11月6日)
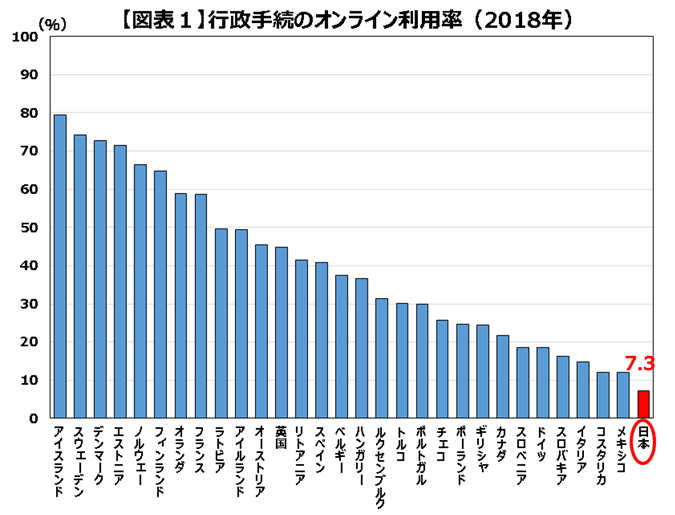
(資料)OECD
行政手続のオンライン利用率のランキング上位は、スウェーデン、デンマークなどの北欧諸国が占めています。北欧諸国では、行政手続だけにとどまらない社会全体のデジタル化が進められています。
例えば、第4位のエストニアは、90年代から徹底して電子国家化に取組んだことで有名です。エストニアでは、原則すべての国民に、免許証、健康保険証などの機能を兼備えた電子IDカードの保有が義務付けられています。また、企業の設立や税務申告などをはじめ、99%もの行政手続をオンラインで完結させることができます。
「行政のデジタル化」が目指すもの
2019年に策定された「デジタル・ガバメント実行計画」では、行政のデジタル化は「Digitalization(デジタライゼーション)」の観点から取組むことが必要だと述べられています。デジタライゼーションとは、紙ベースの従来の手続きをただデジタルに置換えるだけではなく、デジタル化を前提に次の時代の新たな社会基盤の構築を目指す、という考え方です。
これまで、日本の行政手続においては、①紙の添付資料や押印を求められることが多い、②縦割行政の影響でシステムの統一・標準化がなされていない、等の理由から、なかなかオンライン利用が広がっていませんでした。このような現状を打破するため、①デジタルファースト:個々の手続き・サービスが一貫してデジタルで完結する、②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする、③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続き・サービスをワンストップで実現する、という3つの原則のもとで、デジタル化に向けた取組みがなされてきました。
しかし、実行計画で目指した行政のデジタル化が実現される前に、新型コロナウイルスの感染が拡大しました。一人あたり10万円の特別定額給付金のオンライン申請におけるトラブルや、国への感染者発生報告がFAXでなされていたこと等、行政のデジタル化の遅れが指摘されたのは記憶に新しいところです。
デジタル庁創設による行政のデジタル化の進展に期待
コロナ禍によって、現在、行政のデジタル化の流れは加速しています。菅義偉首相はデジタル社会の形成に関する司令塔としてデジタル庁を創設することで、これまで行政のデジタル化が進んでこなかった原因の1つである行政の縦割りの打破を目指します。デジタル庁では、自治体のデジタル基盤の共通化や国の情報システムの整備・管理、マイナンバーカードの普及推進などが進められます。
菅政権は2021年9月のデジタル庁創設を目指しており、行政のデジタル化が進むと、私たち行政サービスの利用者の負担が減少したり、行政サービスの質が向上することが期待できます。行政のデジタル化を巡る今後の動きに注目です。
(ニッセイ基礎研究所 坂田 紘野)
筆者紹介

