第82回 資産形成には若さが最大の武器!?複利と「72の法則」
3分でわかる 新社会人のための経済学コラム2016年12月1日
資産形成で重要な「複利」とは?

「資産形成を始めるのは早いほうがいい」とよく言われます。今回は、その理由でもある複利について紹介します。
複利運用とは、一定期間ごとに配当や利息を元本に繰入れ、次の期間はこの元利合計を元本として運用することです。それに対して、単利運用とは、当初元本のみを運用し続ける方法をいいます。両者の違いは、配当や利息を再投資するかどうかです。
複利と単利で、運用成果はどれほど変わるのでしょうか。100万円を年率+3%で10年間運用したと仮定します。そうすると10年後に、単利だと130万円、複利では134万円になります。

(資料)ニッセイ基礎研究所作成
「10年間も運用して4万円しか変わらないのか」と思う方も、いるかもしれません。では、100万円を年率+3%で運用した場合、資産が2倍になるのに、何年かかるかを計算してみましょう。複利だと24年、単利だと34年かかります。10年も早くなるのであれば、意外と効果が大きいと言えるでしょう。
期間が長いほど複利の効果が大きい
10年間の運用だと複利の効果が小さく見える一方、資産を2倍に増やすのにかかる年数を比較すると、効果が大きく見えるのはなぜでしょうか。
それは資産を2倍にするには30年前後と長い期間かかりますが、期間が長くなるほど、複利の効果は指数関数的に大きくなるからです。
100万円を年率+3%で運用した場合、運用期間によって複利と単利の差が、どれほど生じるのか確認してみましょう。運用期間が10年だと、複利と単利の差は4万円、20年で21万円、30年で53万円。40年だと106万円と、元本以上の差となります。運用期間が長ければ長いほど複利は効果を発揮します。つまり時間というのは、資産形成において大きな武器となるのです。
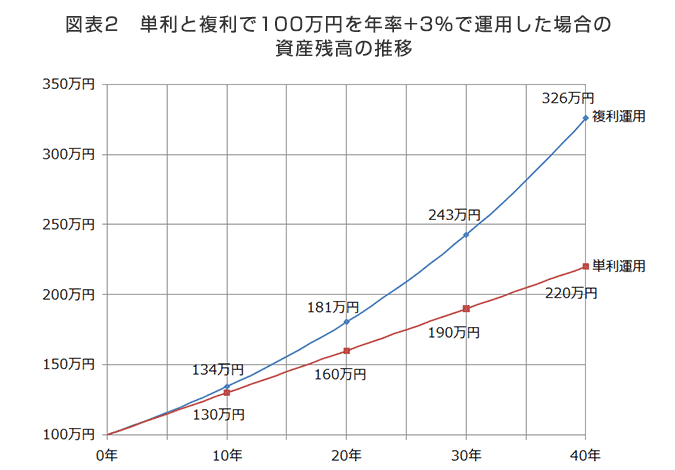
(資料)ニッセイ基礎研究所作成
利回りが高いほど複利の効果が大きい
利回りも複利の効果にとって重要です。年利+0.001%、+3%、+6%、+9%の4つのケースで、どれほど運用成果に差が生じるのか比較してみましょう。年利+0.001%だと40年後も運用資産は100万円のままですが、+3%だと326万円、+6%だと1,029万円、+9%だと3,141万円となります。
利回りが高いほど複利の効果を享受できます。また一定以上の利回りがないと、ほとんど複利効果が期待できません。現在のような低金利環境下で複利運用をするにあたっては、リスク資産も組込み、ある程度の利回りを期待できる運用を行うことが重要だと言えるでしょう。
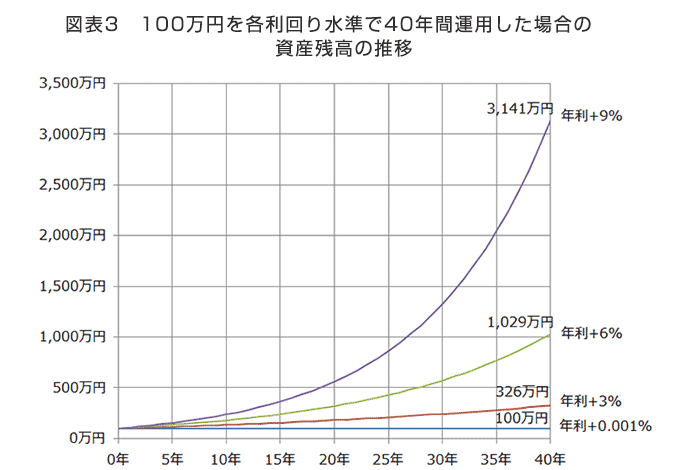
(資料)ニッセイ基礎研究所作成
複利はデコボコ道が苦手
ただし、いたずらに高利回りを狙えばいいのかというと、そうでもありません。高利回りの運用には、リスクがつきものです。大きく儲けることもあれば、大きく損することもあります。安定的にプラスの収益を上げた場合と、プラスとマイナスを繰返した場合、運用成果はどのように変わるのでしょうか。
毎年+3%で運用した場合と、奇数年+12%・偶数年-6%の運用となった場合を比較してみましょう。40年後に、前者は326万円となるのに対して、後者は280万円にとどまり、年を追うごとに両者の差が大きくなります。
大きなマイナスを計上せず、安定的にプラスの収益を獲得することが資産を増やすためには重要なのです。実際に安定的にプラスの収益を上げるというのは、とても難しいことですが、分散投資によりリスクを軽減するというのは一つの対応策と言えるでしょう。
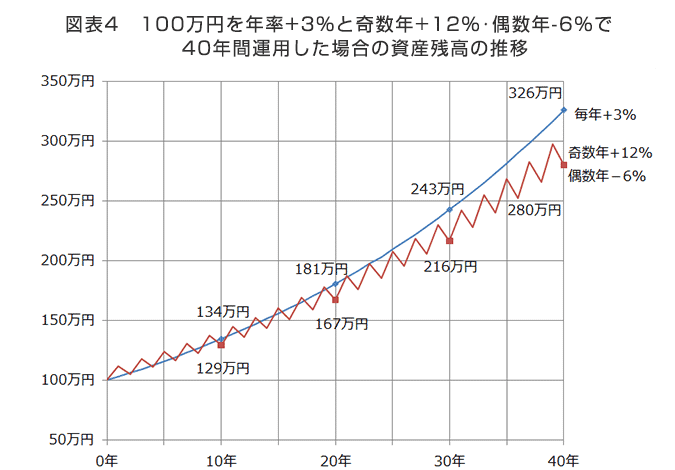
(資料)ニッセイ基礎研究所作成
72の法則
ここまで一定以上の利回りで長期運用すれば、大きな複利効果が享受できるということを説明しました。ただし、複利運用の成果を暗算で計算するのは難しく、とっつきにくいという印象を持った方も多いかもしれません。そこで最後に、複利効果を簡単に計算できる「72の法則」を紹介します。
「72の法則」は、複利で運用した場合に、資産が2倍になるのにかかる大体の年数を計算する方法です。
72 ÷ 利回り = 2倍になるのにかかる年数
この法則を使えば、年率+3%であれば2倍になるのに24年(72÷3)かかることがわかります。これは冒頭で示した結果と同じです。また+6%であれば12年(72÷6)+9%であれば8年(72÷9)かかるということがわかります。
ここでおすすめしたいのが、まず何年後までに2倍にしたいという目標をたて、次に必要とされる利回りを求める使い方です。例えば、10年後までに資産を2倍にしたいという目標をたてた場合、7.2%以上の利回りが必要となることがわかります。
新社会人のみなさんは、いつまでに資産を2倍にしたいと思いますか?
12月といえば、冬のボーナスが支給される方も多いのではないでしょうか。ここで少し我慢して、資産形成にお金を回せば、複利の効果で将来、大きな差を生むかもしれません。
(ニッセイ基礎研究所 佐久間 誠)
筆者紹介

佐久間 誠(さくま まこと)
株式会社ニッセイ基礎研究所、金融研究部、研究員
研究・専門分野:不動産市場、金融マーケット全般
