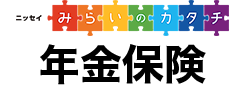預貯金だけで本当に十分?さまざまな方法で資産形成しよう
資産形成
2023.09.08

前回は、幅広い分野で物価上昇する=「インフレ」の時代には投資運用をはじめとした資産形成も考えていかなければいけない、というお話をしました。「何かしなければ」と思ってはいるものの、具体的に何からはじめればよいのかわからなくて、一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。投資には様々な運用方法があるので、それぞれのリスクを理解したうえで、自分に合う方法を検討することが大切です。
投資運用において、「こわい」「わからない」「面倒くさい」はNG!
これまでは、物価が下がり続け、お金の価値が上がり続ける=デフレ時代が長く続いていました。私たち生活者は節約だけで何とかなっていた時代が長すぎて、なかなか投資運用に目が向きづらい環境だったので、投資運用には「こわい」「わからない」「面倒くさい」というイメージを抱きがちかもしれません。でもこの3つのワードは、投資運用においてはネガティブワードです。
まず「こわい」「わからない」というのは、勉強不足からきていますから、投資運用の本を1冊読む、金融機関のサイトの情報を見るなどして、ある程度勉強して理解すれば、ネガティブな気持ちは解消するでしょう。「面倒くさい」のは、初めてのことだから。
しかも投資運用というのは「まとまったお金が必要」というイメージが強い。でも今は、そういう時代ではありません。1000円から投資できますし、クレジットカードで貯まったポイントで投資できるポイント投資もありますから、まずはやってみること。
また投資運用は難しいというイメージがありましたが、今は手数料が無料だったり、無料の取引ツールが使えたりと、環境はかなり整ってきています。税制面でもかなり優遇されつつあります。
自分のスタンスで投資運用しましょう

前回もお話ししたとおり、投資運用は「長期・積立・分散」が基本ですが、改めて投資をする初心者の方にお伝えしたい3つの注意点があります。
1一気にお金を入れない
「卵は1つのカゴに盛るな」という投資の格言がありますが、たくさんの卵を1つのカゴに盛ってしまうと、カゴごと落としてしまったら卵が全部割れてしまうけれど、複数のカゴに盛っておけば、1つのカゴが落ちても他のカゴは大丈夫。つまり1つの商品に集中投資するのではなく、いろいろな商品に分散しましょうということです。その意識を持っておくことは大切です。
2知らないものに手を出さない
これも投資の格言ですが「遠くのものは避けよ」という言葉があります。よく知らない分野やわからない商品に手を出してはいけない。また情報の少ないものには手を出さないようにしようという意味です。いろいろな情報があっても、どこか遠くの国のことだと、それが本当かデマかも判断できませんから。
3人の話に惑わされない
投資初心者は周りの意見に左右されがち。人がもうかった話を聞くと、つい「自分も」となりますが、変なもうけ話にはのらないこと。投資運用でお金を増やすことに近道はありません。近道をしようとして「退職金を持っていかれた」というのはよく聞く話。でもふだんから勉強して、少額でも投資して、自分なりの投資スタイルを持っておけば、怪しい話をもちかけられても避けられるはずです。
基本的に投資は自己責任です。だからこそ、自分はリスクをどれだけとれるか自分で判断し、それに合った運用方法、商品を選んでいくことが大切なのです。
税制メリットのある3つの制度

所得は増えないのに、物価は上がるし、税負担は増えるしで、なかなか可処分所得(収入の中から生活費に回せるお金のこと)の増えない時代。そこで国は投資運用をはじめとした資産形成について、おトクになる制度を準備しています。大きくは3つ。
1つ目は「NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)」です。現状は、上場株式や投資信託で運用できる「一般NISA」と、金融庁の基準を満たした投資信託で積立運用する「つみたてNISA」があり、これはどちらかしか口座を開けません。
「ジュニアNISA」もありますが、これは2023年で終了となります。
2023年までのNISA口座は一般NISA、つみたてNISAのどちらか一方の口座で運用ができ、一般NISAは5年間、年間120万円まで、つみたてNISAは20年間、年間40万円までが非課税投資枠になります。
2024年からは「一般NISA」と「つみたてNISA」を組み合わせた「新NISA」がスタートします。ちなみに、NISA口座で運用して出た運用益などにかかる源泉分離課税20.315%が非課税になるのがメリットです。ちなみに2023年までのNISA口座と別枠で新たに口座を開設することができます。
2つ目は保険会社が販売する「個人年金保険」。iDeCoと同様に年金にプラスできるし、自分で 運用せずに、保険会社にお任せできて楽なので、初心者の方にもおすすめ。しかも年間上限4万円の所得税と、上限2万8,000円の住民税に個人年金保険料控除が適用されます。
さらに3つ目は「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」。自分で掛金と運用方法を決めて年金を積み立てていく制度。引き出しは原則60歳以降です。掛金は全額所得控除の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。また通常、金融商品を運用して出た運用益には、源泉分離課税20.315%が課税 されますが、iDeCoなら非課税で再投資されます 。さらに、年金を受け取るときも税制優遇がある、と税制的なメリットがトリプルで受けられます。
| 現行NISA(~2023年) | 新NISA(2024年1月~) | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
| 対象者 | 国内に居住する18歳以上の方 | |||
| 年間非課税額 | 年間120万円 | 年間40万円 | 年間240万円 | 年間120万円 |
| 非課税期間 | 5年 | 20年 | 無制限 | |
| 累計非課税投資上限額 | 600万円 | 800万円 |
1,800万円 (うち成長投資枠1,200万円) |
|
| 運用商品 |
上場株式、投資信託 (ETF・REIT含む) |
金融庁の基準を 満たした投資信託 |
上場株式、投資信託等 (一部対象除外あり) |
金融庁の基準を 満たした投資信託 |
| 併用 |
一般NISAとつみたてNISAは 併用不可 |
可能 | ||
| 中途引き出し | いつでも可能 | |||
| 個人年金保険 | iDeCo | |
|---|---|---|
| 対象者 | 商品により異なる |
国民年金被保険者である 20歳~65歳未満の方 |
| 年間控除上限額 |
所得税計算で年間4万円、 住民税計算で年間28,000円 |
14.4万円~81.6万円 (職業、他の年金制度への 加入状況によって異なる) |
| 非課税期間 | 商品により異なる | 運用期間中 |
| 累計非課税 投資上限額 |
- | - |
| 運用商品 | 商品により異なる |
元本確保商品・投資信託・ 生命保険 |
| 併用 |
どちらも一般NISA・つみたてNISA どちらかと併用可能 |
|
| 途中引き出し |
可能 (解約の時期によっては 元本割れの可能性あり) |
原則60歳まで引き出し不可 |
- ※iDeCoについて、下記の方は加入対象となりません。
- ・農業者年金の被保険者
- ・国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている方(ただし、障害基礎年金を受給されている方等は加入できます)
- ・iDeCoの老齢給付金を受給(一括受け取りを含む)している、したことがある方
(企業型DCの老齢給付金を受給している、したことがある方はiDeCoに加入できます) - ・老齢基礎年金の受給権がある方
- ・特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している方
- ・お勤め先で加入している企業型確定拠出年金の事業主掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方
- ・マッチング拠出(加入者も掛金を任意で拠出)を導入している企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者の方で、企業型DCでのマッチング拠出を選択した方
これから投資運用をはじめとした資産形成を行う人は、まずこうした税制メリットのある制度を利用すべきなのは、いうまでもありません!
今回のまとめ
11000円からでもまず投資してみることが大切!
2投資は自己責任。リスクは自分で判断を!
3税制メリットのある、国の制度を利用すること
監修者プロフィール

節約アドバイザー‧ファイナンシャルプランナー‧
消費⽣活アドバイザー
丸⼭晴美(まるやま‧はるみ)さん
22歳で節約に⽬覚め、1年で200万円を貯めて26歳でマンションを購⼊。その体験をもとに節約アドバイザーとして独⽴。ファイナンシャルプランナー(AFP)、消費⽣活アドバイザーなどの資格も取得し、メディアや講演でおトクなマネー情報を発信し続けている。『お⾦を活かす ハッピーエンディングノート』(東京新聞)、『かんたん申請で「⽉5万円」もらえる! シングルママの「お⾦に困らない」本』(徳間書店)、『50代から知っておきたい! 年⾦⽣活の不安、解消します』(共著・幻冬舎)など著書多数。
- ※当社から丸山さんに取材・監修を依頼し編集のうえ掲載しています。