第149回 Z世代の「16」年間
新社会人のための経済学コラム2022年7月5日
Z世代とは

昨今「Z世代」という言葉をよく聞くと思いませんか?Z世代とは、主に欧米で議論されてきた世代論のことで、1996年から2012年の間に生まれた若者の事をさします。日本においては、2020年アメリカ合衆国大統領選挙関連の報道で、新しい価値観を持つ彼らの1票が注目され、Z世代に関する特集が多く組まれていた印象を受けます。それに伴い、日本における若者もZ世代というラベリングがされ、主に消費行動の視点から彼らの特徴が考察されてきました。
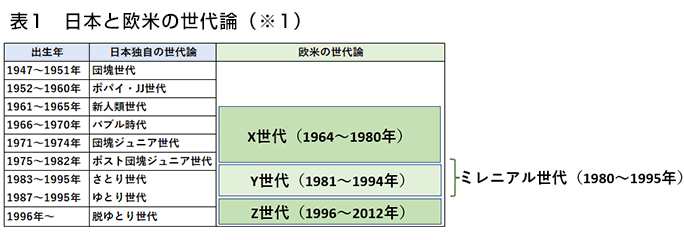
出所:筆者作成
3つの消費の特徴
筆者は、Z世代の消費行動には①デジタルネイティブ、②フリーミアム、③サブスクリプションの3つの特徴があると考えています。
まず、①デジタルネイティブですが、Z世代が生まれた時から消費方法の選択肢にインターネットを使用するという手段が存在していました。1999年には、Yahoo! JAPANにより、日本向けYahoo!オークションがサービス開始され、2000年にはアマゾンジャパンがサービスを開始しました。それ以前の世代が、インターネットの登場に伴い、消費の方法としてインターネットを受け入れる必要があったのに対して、Z世代は、むしろインターネットショッピングという選択肢がない時代を知らないのです。
次に②フリーミアムですが、フリーミアムとは基本的なサービスや製品を無料で提供し、更に高度なサービスや機能に関しては有料で行う事により収益を得るビジネスモデルをさします。基本プレイ無料のスマホゲームはその身近な例と言えます。また、新型コロナウイルス流行に伴い、普及した「Zoom」をはじめとしたオンラインミーティングツールにおいても基本無料サービスと、より充実した有料サービスを消費者は選ぶことができます。Z世代の周りにはそのようなフリーミアムな消費を行う機会が多く、無料で消費することで満足できるモノならばわざわざお金を払う必要がないという価値観を擁している消費者もいます。一方でスマホゲームなどへの課金や、自分が推している人に対して「投げ銭」と呼ばれるインターネットを通じた送金を行うなど、サービスの拡充やコンテンツを支援するために自ら進んで支出を行うという価値観も定着しつつあります。
③サブスクリプションは定期購読という意味です。昨今では動画配信に限らず、さまざまな商品やサービスがサブスクリプションの対象になっています。経済学者であるセオドア・レビット氏は「ドリルを買いにきた人が欲しいのはドリルではなく『穴』である」という有名な格言を残していますが、Z世代の中にはわざわざ手段に必要なモノを購入するのではなくサブスクリプションやレンタルを利用することで目的を達成するという価値観を持つ消費者も増えています。
また、インターネットの普及に伴い情報量が増えたことで、Z世代は以前の消費者に比べて興味を刺激される機会が多くなっています。中でもSNSの普及により、SNSに投稿することで消費が完結する消費文化が定着してきており、SNS上には再現可能な他人の消費結果が溢れています。そのため、Z世代には他人の投稿を消費の疑似体験と捉え、わざわざ自分で消費(購買)する必要があるか、モノを所有する必要があるか、と検討する消費者もいます。
一概にZ世代と言っても
ここまで、Z世代の消費の特徴を3つ挙げました。これは、彼らが生きてきた時代の中で生まれた普遍的な市場の変化によって構築されていった特徴や価値観と言えます。しかし、一概にZ世代と言っても1996年から2012年の16年間に生まれた層の全てが含まれるわけで、2022年現在の年齢で言えば10歳から26歳を指すのです。その中では大きな市場の変化とは別に、小さな市場変化やトレンドが生まれているわけです。この16年間を電子機器市場という側面から見れば、1996年はバンダイの「たまごっち」が、2012年はアップルの「iPhone5」が市場のトレンドであり、同じZ世代といっても消費してきたモノに大きな違いがあるのです。
2001年生まれのZ世代の場合
では、実際にZ世代が育った時代を見てみましょう。図1,2は2001年生まれのZ世代の年表です。彼らが生まれた2001年は東京ディズニーシーが開業しており、同じディズニーリゾート旅行でも生まれた時からディズニーランドに行くか、ディズニーシーに行くかという選択肢があったわけです。また、幼少期には「iPhone」が誕生し、小学生でスマートフォンを擁していた子どもたちも散見できました。10歳の頃には人気ユーチューバーの「ヒカキン」が活動を開始しています。サムライト株式会社による動画専用プラットホームの利用率調査をみるとZ世代のYouTube利用率は82.8%であり、今やYouTubeは若者に欠かせないプラットホームになっています(※2)。この頃には現在では当たり前となったYouTuberという職業の萌芽を垣間見ることができたわけです。2016年、彼らが中学生だった頃、世界での興行収入414.4億円を記録した新海誠の映画「君の名は」やエンディングテーマの恋ダンスが社会現象を生んだドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」など、ブームを生んだコンテンツが誕生しました。高校在学中には元号が「令和」に代わり、2020年彼らが大学に入る年、新型コロナウイルスが流行し、彼らはステイホームという新しい生活様式の中で大学生活を過ごしてきたのです。2022年現在、彼らの多くは大学3年生となり、中にはインターンシップなど就職活動を開始する者もいます。大学生活のほとんどをオンラインで行ってきた彼らの大学生時代の経験や思い出などは、それ以前の世代とは大きく異なっており、面接を設ける企業の人事担当者にとってもギャップを感じる局面もでてくるでしょう。
筆者自身は世代論は、その世代に対するある種レッテルを貼る行為であり、あたかもその世代の人が全てそのような価値観、特徴を擁しているように語られることに対して妥当性があるとは考えていません。しかし、例えば新型コロナウイルス流行といった社会変化やIT革命による市場の変化は、平等に全ての消費者が影響を受けることであり、その変化をいつ受けたのか、また「iPhone」や「君の名は」といった特定の対象物を消費したのは何歳の頃だったのか、という世代間の変化をみることは、その世代の消費の特徴を認識するうえで重要な視点であると筆者は考えるのです。
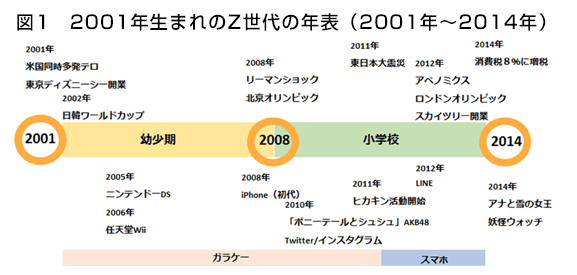
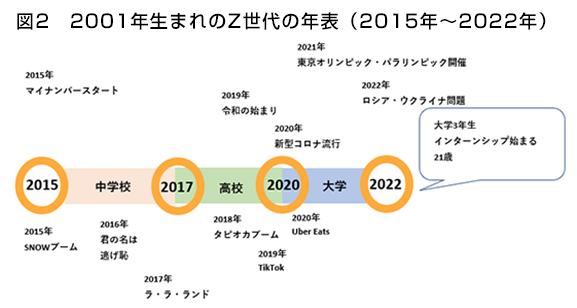
出所:筆者作成
-
(※1)研究者や研究領域によって定義の仕方が異なる
-
(※2)
(ニッセイ基礎研究所 廣瀨 涼)
筆者紹介

廣瀨 涼(ひろせ りょう)
株式会社ニッセイ基礎研究所、生活研究部 研究員
研究・専門分野:消費文化、マーケティング、ブランド論、サブカルチャー、テーマパーク、ノスタルジア
