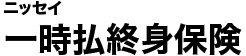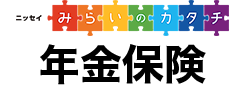退職金にかかる税金とは?計算方法や確定申告についてわかりやすく解説
読了目安:約6分
税制/制度
2025.09.24

退職金は「退職所得」として、所得税と住民税の課税対象です。ただし、長年の勤労に対する感謝の意味から、退職所得控除や2分の1課税など、税制上の優遇措置が設けられています。
また、受け取り方によって課税方法が異なります。一括受け取りと年金受け取りのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に応じて最適な選択をしましょう。
〈この記事でわかること〉
- ・退職金には「住民税」「所得税」がかかるが、税制上の優遇制度がある
- ・受け取り方法で「一時金受取」を選択すれば、まとまったお金を計画的に活用できる
- ・iDeCoや個人年金保険を活用すれば、より手厚く老後資金を用意できる
退職金に税金はかかる?
退職金は所得税の中でも「退職所得」に分類され、課税されます。勤続年数に基づいた控除額を計算し、退職金が控除額を上回る場合、所得税(復興特別所得税含む)と住民税が発生する仕組みです。ただし、退職金には特別な税制優遇があります。
退職金にかかる税金は?
退職金にかかる税金は、所得税と住民税の2つです。それぞれ、計算の流れは以下のとおりです。
- 1.退職所得控除額を計算する
- 2.課税対象額を計算する
- 3.税率表に当てはめて税額を算出する(住民税は10%)
なお、退職所得は他の所得と合算しない「分離課税」です。 給与所得や事業所得などとは合算せず、「退職金は退職金のみで、別途税金を計算する」というイメージを持つとよいでしょう。
退職金に税制優遇はある?
退職金には長年の功労に感謝する意味合いがあり、「退職所得控除」や「2分の1課税」など税負担を軽減する措置が設けられています。
退職所得控除の計算式は、以下のとおりです。
| 勤続年数 | 控除額の算式※ |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円の最低保証あり) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数–20年) |
- ※障がい者になったことが直接の原因で退職した場合、100万円を加えた金額となる
なお、勤続年数に1年未満の端数日がある場合、繰り上げて計算します。たとえば、勤続年数が「20年1日」だった場合、勤続年数を21年として退職所得控除を計算します。
「2分の1課税」とは、退職金から退職所得控除を差し引いた金額の、2分の1を課税対象とする仕組みです。たとえば、受け取った退職金が2,000万円で退職所得控除が1,500万円の場合、「(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円」が、課税対象です。
なお、2022年(令和4年)1月1日以後、勤続年数が5年以下の人(役員等以外)が受け取る退職金は、300万円を超える部分は「2分の1」とならず全額が課税対象です。
退職金を受け取った翌年の税金は高くなる?
退職金に対して発生する所得税と住民税は、支給時に源泉徴収されるため、受け取った方が個別で納付する必要はありません。つまり、退職金に関する課税関係は、退職金を受け取った年で完結します。
ただし、給与所得に対する住民税に関しては、給与を受け取った翌年の6月以降に反映されます。離職している場合は、自分自身で納税する「普通徴収(納税のタイミングは年1回または年4回)」になるため、「税金が高い」と感じるかもしれません。
住民税は後払いのシステムであり、当年の給与が翌年に反映される点を押さえておきましょう。納税資金不足の対策として、退職金の一部を納税資金として確保しておくと安心です。
退職金にかかる税金をシミュレーションで確認

実際に、退職金に対してどの程度の税金が発生するのかを見ていきましょう。勤続10年で500万円の退職金を受け取ったケース、勤続38年で2,100万円の退職金を受け取ったケースでシミュレーションします。
- ※本シミュレーションはあくまで簡易的な計算例です。実際の税額は、退職所得申告書の提出の有無やその他の所得、個々人の状況によって異なります。正確な税額については、税務署や税理士などの専門家にご確認ください。
中途入社で勤続10年【退職金500万円】
まずは、勤続10年で500万円の退職金を受け取ったケースを見てみましょう。

| 勤続年数 | 10年 |
|---|---|
| 退職所得控除額 | 400万円(40万円×勤続年数(80万円の最低保証あり)) |
| 退職所得 | 50万円 |
| 所得税(退職所得をもとに計算) | 2万5,000円(50万円×5%)※復興特別所得税は含まず |
| 住民税(退職所得をもとに計算) | 5万円(50万円×10%) |
| 退職金の手取り額 (退職金-所得税-住民税) |
492万5,000円 |
「退職所得控除400万円<退職金500万円」となるため、退職金から退職所得控除を差し引き、さらに2分の1を乗じた50万円が課税所得です。所得税と住民税をあわせて、約7万5,000円の税金が発生します。
新卒から定年まで勤続38年【退職金2,100万円】
次は、勤続38年で2,100万円の退職金を受け取ったケースです。
| 勤続年数 | 38年 |
|---|---|
| 退職所得控除額 | 2,060万円(800万円+70万円×(勤続年数−20年)) |
| 退職所得 | 20万円 |
| 所得税(退職所得をもとに計算) | 1万円(20万円×5%)※復興特別所得税は含まず |
| 住民税(退職所得をもとに計算) | 2万円(20万円×10%) |
| 退職金の手取り額 (退職金-所得税-住民税) |
2,097万円 |
「退職所得控除2,060万円<退職金2,100万円」となり、退職金から退職所得控除を差し引き、さらに2分の1を乗じた20万円が課税所得です。今回のケースでは、所得税と住民税を合わせて約3万円の税金が発生します。
退職金の受け取り方で税金が変わる?
企業によっては、退職金は一括で受け取るか、年金のように分割して受け取るかを選択できます。どのように受け取るかで課税方法が異なるため、それぞれの特徴と税金面での違いを整理しましょう。
一括受け取り
「一括受け取り」とは、まとまった金額を一度に受け取る方式です。「一時金」とも呼ばれ、一括で受け取ると「退職所得」として、分離課税で扱われます。
退職所得には、退職所得控除や2分の1課税が適用されるため、税金の負担を抑えられます。また、翌年の社会保険料にも反映されません。
税金と社会保険料負担を抑えたいと考えている方は、一括受け取りが向いているでしょう。また、住宅ローンの繰り上げ返済や子どもの教育資金など、退職後にまとまった金額が必要な方も、一括受け取りがおすすめです。
ただし、退職金の大半を住宅ローンの繰り上げ返済に回した結果、手元資金が枯渇する可能性がある点には注意が必要です。退職後の支出の予定を把握したうえで、資金計画を立てましょう。
年金受け取り
「年金受け取り」とは、5〜20年など決められた期間・回数に分けて退職金を受け取る方式です。年金形式で受け取る場合、「雑所得」として扱われ、総合課税の対象です。
具体的には、受け取った年金額から公的年金等控除を差し引き、公的年金や給与など他の所得と合算したうえで、所得税や住民税が計算されます。年金受け取りの場合は、翌年の社会保険料に反映されるため、国民健康保険料や介護保険料などの負担が重くなる可能性があります。
一方で、分割して退職金を受け取れるため、定期的な収入があると安心できる方は、年金受け取りが向いているでしょう。
また、長生きリスクに備えるための効果的な対策として、公的年金の繰下げ受給があります。公的年金は1ヵ月受給を繰り下げるごとに0.7%増額(最大84%)され、増額された年金額は一生涯続きます。
公的年金を繰下げ受給する場合、繰上げ期間中の生活費をまかなう目的で、退職金を年金で受け取るという方法も検討する価値があるでしょう。
退職金に確定申告は必要?
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職金に関する確定申告は不要です。勤務先が源泉徴収と納税を代行するため、本人が納税をする必要はありません。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取った場合、一律20.42%の率で源泉徴収されます。退職所得控除と2分の1課税が適用されていないため、必要以上に納税している可能性が高いでしょう。
この場合、確定申告をすることにより、本来の税額を超えて源泉徴収された部分に関しては還付を受けられます。翌年3月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が期限)までに確定申告を行い、精算・還付を受けましょう。
退職金の平均はどれくらい?
退職金の平均額は、企業規模や業種、勤続年数などによって異なります。大企業と中小企業ごとに、退職金の平均を確認しましょう。
【大企業】
| 定年退職 | 会社都合 | 自己都合 | |
|---|---|---|---|
| 退職金額 | 約1,878万円 | 約1,400万円 | 約488万円 |
【中小企業(定年退職)】
| 高卒 | 高専・短大卒 | 大卒 | |
|---|---|---|---|
| 退職金額 | 約974万円 | 約992万円 | 約1,150万円 |
実際には、企業ごとに退職金制度の詳細や計算方法は異なります。就業規則や退職金規程などに目を通し、受け取れる金額の目安を把握しておきましょう。
老後資金を準備するポイント
退職金は、公的年金と並んで老後資金の柱となる資金です。無計画に使うと老後資金が枯渇してしまう可能性があるため、計画的な取り崩しと運用を意識しましょう。
まとまった資金を活用したい方はこちら!
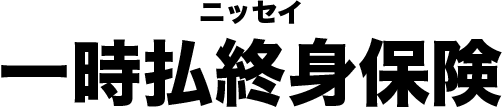
- 死亡保険金ですぐに使える資金を準備できます
- 保険金は一定額まで非課税
- ※詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。
退職後の収入計画を立てる重要性
老後生活に突入すると、自由時間が増える一方で、病気やケガのリスクが高まります。日常生活費だけでなく、趣味を楽しむための娯楽費や医療費・介護費などの支出が発生することを見据えて、退職後の資金計画を立てましょう。
生活費は公的年金でまかない、娯楽費と医療費・介護費は退職金の取り崩しでまかなえると、経済的に安心できます。特に、医療費と介護費は「いつ発生するか」「いくら発生するか」が事前に読みにくいため、退職金の一部をためておきましょう。
iDeCoや個人年金保険などの活用もおすすめ
現役の頃に、iDeCo(個人型確定拠出年金)や個人年金保険を活用して、自分専用の年金を作ることも一案です。退職金に加えて、さらに老後資金を上乗せで用意できれば、老後の安心感は大きくなります。
iDeCoは拠出した掛金が全額所得控除の対象で、運用益は非課税です。税制面のメリットが大きく、節税しながら老後資金を作れる制度として、有効活用できます。
個人年金保険は、一定の条件を満たしたときに「個人年金保険料控除」が適用されます。所得税は4万円(旧個人年金保険料控除では5万円)、住民税では2万8,000(旧個人年金保険料控除では3万5,000円)円を上限として、所得控除を受けられます。
まとめ
退職金を一括で受け取ると、退職所得控除や2分の1課税により、税金の負担を軽減できます。場合によっては非課税となることもあるため、手取り額を増やしたい方は、一括受け取りが有力な選択肢です。
一方で、年金受け取りなら安定した収入を確保できます。定期的な収入があったほうが安心できる方は、年金受け取りを選択するとよいでしょう。
「どちらの受け取り方法が優れているか」は一概にいえません。退職時の資産状況や支出の予定などに応じて、適した方法を選択しましょう。
監修者プロフィール
ファイナンシャルプランナー(CFP®、ファイナンシャル・プランニング技能士)
續恵美子(つづき・えみこ)
生命保険会社にて15年勤務したあと、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。
渡仏後は2年間の自己投資期間を取り、地元の大学で経営学修士号を取得。地元企業で約7年半の会社員生活を送ったあと、フリーランスとして念願のファイナンシャルプランナーに。生きるうえで大切な夢とお金について伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。