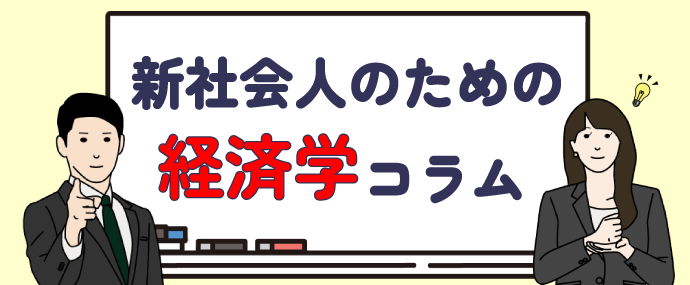第182回 2025年、育児や介護と仕事の両立に向けて育児・介護休業法等が改正
新社会人のための経済学コラム2025年4月10日
育児・介護休業法等改正の概要

2025年、仕事と育児・介護の両立の支援を目的として育児・介護休業法等が改正されます。子どもを育てやすい社会の実現や育児・介護による離職の防止を目指して、企業は働きやすい環境の整備が求められるようになります。今回の法改正は図表1の点が柱となっています。
図表1 育児介護休業法等の改正のポイント
- 柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子の範囲拡大
- 労働者数300人超の企業の育児休業取得状況の公表義務付け
- テレワークの推進
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮の義務付け
(資料 厚生労働省「育児・介護休業法について」をもとに筆者作成)
それぞれについて見ると、まず柔軟な働き方を実現するための措置の義務付けが強化されます。小学校就学前の子どもを育てる労働者に対し、企業は始業時刻の変更やテレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与などを提供し、労働者が選択できるようにする必要があります。これにより、仕事と育児の両立がしやすくなることが期待されます。
次に、子の看護休暇の見直しが行われます。従来、就学前の子どものいる労働者のみが対象でしたが、改正後は小学校3年生までの子どものいる労働者も看護休暇を取得できるようになります。また、学級閉鎖や入学式・卒園式などの学校行事にも休暇を利用できるようになり、働く親はこうしたことに対応しやすくなります。
また、所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子の範囲が拡大されます。これまでは3歳未満の子どものいる労働者のみが対象でしたが、改正後は小学校就学前の子どものいる労働者も対象となります。育児休業取得状況の公表が義務付けられる企業の対象範囲が拡大されます。これまでは1,000人超の企業のみが対象でしたが、300人超の企業にも義務付けられることで、育児休業の取得状況が可視化され、特に男性の育児休業取得が進むことが期待されます。
テレワークの推進も今回の改正の重要なポイントです。特に、3歳未満の子どもを育てる労働者や介護を行う労働者に対し、企業はテレワークを行える労働環境の提供が求められます。これにより、通勤の負担が軽減され、家庭と仕事の両立がしやすくなることが期待されます。
また、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援も強化されます。企業は、労働者が家族の介護に直面した際、支援制度を個別に周知し意向を確認することが求められます。この措置により、労働者が急な介護負担に直面した場合に支援を受けやすくなると期待されます。
さらに、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮の義務付けが行われます。企業が労働者一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応を行うことで、労働者が安心して働き続けられることが期待されます。
育児・介護がしやすい働き方が求められる背景
育児・介護休業法等の改正が行われる背景には共働きの普及などによって働き方が変化する一方で、労働環境・制度はそれに対応しきれておらず課題が残されている点があります。
内閣府男女共同参画局によれば、近年では女性の就業率は上昇したものの、正規雇用の割合は低いことが示されています(図表2)。年齢階級別の内訳を見ると、正規雇用で働く女性の割合は25~29歳で6割程度と最も高くなるがそれ以降は低下、40歳以降では4割以下まで低下しています。育児などの都合により妻は正規雇用の仕事を退職せざるを得ず、非正規雇用の仕事を行いながら育児を主に担っている実態が考えられます。
政府が掲げる「こども未来戦略」では少子化対策として、夫婦が協力して子育てを行う社会の実現を目指しています。子育てをしやすく働きやすい社会・職場を実現するうえでは、こうした家庭の変化を踏まえることが求められます。
また、介護についても高齢化により要介護者が増加するとともに、家庭内での介護の担い手が変化しています。厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、2000年代では同居の主たる介護者の続柄は子の配偶者(妻)が多かったが、近年では子が担う場合が増えています。
以前は一般的だった正規雇用の夫と専業主婦の夫婦では夫の親の介護を妻が行う場合も多かったものの、近年では共働き夫婦の増加により夫の親の介護は夫が行うように変化しています。
介護や育児は、それまでは行っていなかった人も担うことが必要な状況となり得ます。これにより、規定とおりの時間場所での勤務や生活のほとんどの時間を仕事に費やす働き方が難しくなる場合があります。働き手のライフスタイルが多様化する中では、柔軟な勤務形態や人事制度により就業を継続し従業員の定着を支えることが必要となっています。

図表2 女性の年齢階級別正規雇用比率(L字カーブ)
(資料 内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書令和6年版」をもとに筆者作成)
誰もが働きやすい社会の実現に向けて
今回の改正は、育児・介護の負担を軽減し、労働者がより長く安定して働ける環境を整えることを目的としています。テレワークの推進や残業免除の拡大により、柔軟な働き方が可能になり、育児や介護をしながらも働き続けられる環境が整えられます。また、育児休業取得状況の公表義務が拡大されることで、企業の意識改革が促進され、男性の育児休業取得率向上にも寄与することが期待されます。
しかし、制度が整っても企業の意識改革が進まなければ実効性は低くなってしまいます。そのため、企業と労働者の双方が制度を理解し、活用する意識を高めることが今後の課題となります。
今回の法改正は、育児や介護を理由とした離職を防ぎ、誰もが働きやすい社会を実現するための重要なステップとなります。企業や社会全体の意識改革とともに、実際に制度が活用される環境を整備することが求められます。
(ニッセイ基礎研究所 原田 哲志)
筆者紹介