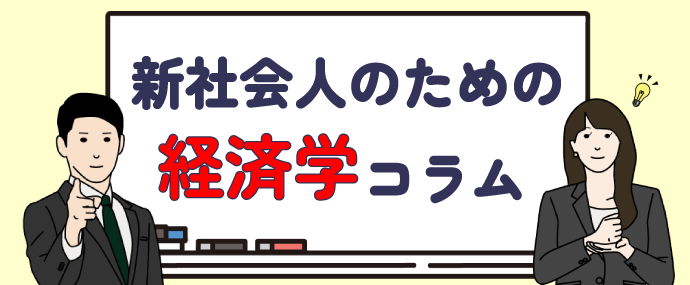第180回 2024年度最低賃金は全国加重平均1,055円、引き上げ幅は過去最大
新社会人のための経済学コラム2025年2月13日
政策主導で進む、最低賃金の改定

今年度の最低賃金の引き上げ幅(改定額)は、物価や春闘の結果を踏まえて過去最大となりました。2024年10月からの最低賃金は全国加重平均額で1,055円となり、昨年度から51円引き上げられることになりました。
最低賃金は、法律に基づいて国が定める賃金の最低限度額です。労働者に対して支払われる賃金がこの水準に達しなかった場合、企業には50万円以下の罰金が科されることになります。日本の最低賃金は、経営者代表、労働者代表、学識経験者(大学教授、研究者、弁護士など)から選ばれる公益代表、各同数からなる審議会の議論で目安額が決まり、その後、各都道府県での協議や調整を経て毎年10月に改定されます。
本来、最低賃金は労使・公益代表の協議により決められるべきものですが、近年は政府の掲げた目標や方針が、最低賃金の改定に大きな影響を及ぼしています。例えば、安倍元首相は2015年に最低賃金を毎年3%程度の目安で引き上げ、将来的に全国加重平均1,000円を目指すとの目標を掲げました。その後、9年間の最低賃金改定率は、コロナ禍が深刻だった2020年の時期を除いて、毎年3%を超える引き上げが実現されています[図表1]。また、全国加重平均1,000円の目標は2023年に達成され、政府は新たな努力目標として2020年代に全国加重平均1,500円を目指す方針を掲げています。仮に、この目標を2029年に達成させるとした場合、今後5年間に毎年7.3%を上回る改定率が必要となります。これは、バブル期を超える改定率が続くことを意味します。
![[図表1]最低賃金の改定状況](/assets/enjoy/keizai/pict_180_02.png)
最低賃金引き上げに見る「光と影」
最低賃金の引き上げは、低賃金労働者の所得増加により、格差縮小や個人消費の活性化につながるとの期待がある反面、労働コストの上昇で企業業績の重荷になるとの懸念があります。
例えば、正規労働者賃金の中央値に対する最低賃金の比率でみると、日本は主要国の中で低いことが分かります[図表2]。この格差が、最低賃金の引き上げで縮小すれば、低賃金労働者への保護はより手厚くなります。また、所得が増えれば、低賃金労働者や家計における生活の質が改善し、消費活動が活発化します。所得の継続的な増加は、日本経済低迷の大きな要因とされてきた個人消費の長期低迷を打開するうえで重要です。
![[図表2]最低賃金の正規労働者賃金の中央値比(推移)](/assets/enjoy/keizai/pict_180_03.png)
ただ、最低賃金の引き上げで、企業の人件費負担は重くなります。とりわけ、ぎりぎりの経営が続く中小・零細企業にとって人件費の上昇は死活問題であり、最悪の場合、企業倒産に至ることも考えられます。そうなれば、労働者の雇用や所得機会の喪失など、最低賃金引き上げの本来の目的とは、まったく逆の結果を招くことになってしまいます。課題は、人件費の上昇だけに留まりません。最低賃金が上がると、昨今、注目が集まる「年収の壁」との関連で、従業員が時間調整する問題(働き控え)が発生しやすくなります。従業員の労働時間が減れば、人手が足りない企業では、更に人手不足は深刻化します。実際、従業員の退職や採用難、人件費高騰などを要因とする「人手不足倒産」は記録的なペースで増えています。如何にして持続的な賃上げを実現し、人手を確保していくのか。企業にとって重要な経営課題となっています。
以上から言えることは、社会全体をより良くしていくには、最低賃金の引き上げだけでは不十分だということでしょう。最低賃金を上げる際には、労働者と企業の両方に目配りし、労働者保護と企業経営支援の政策をセットで組み合わせることが重要です。加えて、賃上げに応じた年収の壁などの制度見直しも欠かせません。最低賃金については、これからも改定幅に注目が集まると思いますが、それと合わせて動く、税制や社会保障、経済対策にも、ぜひ関心を持っていただければと思います。
(ニッセイ基礎研究所 鈴木 智也)
筆者紹介