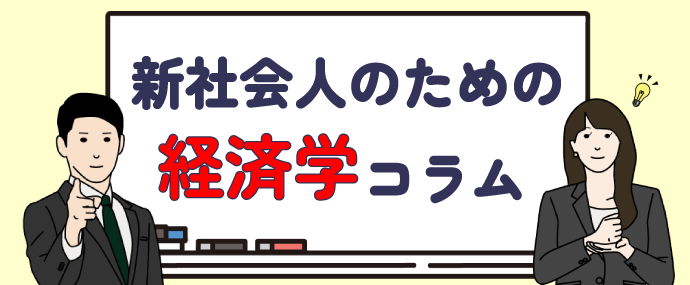第177回 「結局タイパとは何なのか?」
新社会人のための経済学コラム2024年11月14日
あれもこれも「タイパ」

国語辞典などを扱う出版社・三省堂が発表した「辞書を編む人が選ぶ『今年の新語2022』」において、その年を象徴する言葉として「タイパ」が大賞に選ばれました。「タイパ」とは、「かけた時間に対する効果(満足度)」や「時間の効率」を意味する新語です。2021年にファスト映画(ネタバレを含む要約された動画)の投稿によってアップロード主が逮捕されたことがきっかけに注目されるようになりました。違法性のあるファスト映画を人々が消費する背景を探るうえで、メディアが「タイパ(タイムパフォーマンス)」というキーワードに着目し、特に若い世代が消費において時間効率を重視しているという文脈で使われるようになりました。
一方で、筆者は「タイパ」に関連した報道に対して疑問を抱いています。どのメディアでも「タイパ」を「時間対効果のことで、かかった時間に対する満足度をあらわす言葉」として紹介していますが、「若者はファスト映画を視聴している」「倍速視聴が増えている」といった事例と同時に「電子レンジ調理食品でタイパ良く献立作り」「タイパの良い家電ランキング」といった家事における時短追及や、「無駄な会議を減らしてタイパの良い職場に」「リモートワークでタイパ向上」といった業務効率化の議論にも使われています。このように、さまざまなトピックが「時間対効果=タイパ」としてひとくくりにされ、多様な文脈で使われすぎることで、「結局タイパとは何なのか?」という問いが一層複雑になっていると考えるのです。
タイパを理解するための2つの視点
そこで、筆者はタイパが追求される目的を2つに分類しました。1つ目は「時間短縮」の側面です。これは、作業の効率を高め、かける時間を減らすことで、他の活動に使う時間を生み出すことが目的となるタイパです。例えば、家事においては、以前より時短や裏ワザという呼び方で、家電や既成商品・サービスだけでは解消されない家事の効率性を消費者は意識してきました。このような効率化は、家事や仕事など「やらなければならない」タスクを早く終わらせるために使われ、その結果、他の生産的な活動に時間を割くことに繋がります。
2つ目は「特定の状態になるための手段」としてのタイパです。前述したファスト映画やネタバレサイトなどを見てその映画を見た状態になることを目的としたタイパがこれにあたります。映画鑑賞の本来の目的ともいえる感動や喜びのために視聴するのではなく、「観た状態」=「その映画を媒介にコミュニケーションができる状態」になることが目的ならば、必ずしもその映画を観なくてもいいのであり、その目的を達成しうる手段の効率や費用対効果を比較することがこの文脈におけるタイパの本質といえます。
最もタイパ良く宿題を済ます方法は?
この文脈におけるタイパを理解するには、「宿題」を例に挙げるとわかりやすいでしょう。宿題には2つの目的があります(※図1)。1つ目は宿題をすることで学力を高めたり、勉強の習慣をつけることです。これは先生がそもそも学生に宿題を与える理由であり、期待していることでもあります。問題を自分で解くこと自体が目的といえます。
2つ目は、宿題をやっていないことで怒られてしまうリスクを回避することです。別に勉強に興味がない学生にとっては、学力をつけたり、勉強の習慣をつけることを望みはしません。ただ、宿題を提出しないことで先生に怒られたくない場合、宿題を終わらせておく必要があります。この場合、宿題を終わらせておくことが目的のように見えるかもしれませんが、提出が求められなかったり、終わらせてなくても怒らない先生ならば、必ずしも宿題を済ませておく必要はありません。そのため、本当の目的は「(宿題をやっていないことで)怒られることを回避できる状態」になっておくことにあるわけです。
図1 宿題を済ますことの目的
-
①宿題をすることで学力を高めたり、勉強の習慣をつける⇒問題を解くこと自体が目的となる
-
②宿題をやっていないことで怒られない状態になる⇒宿題を終わらせた状態にするための手段は複数ある
出所:「タイパの経済学」p.114を基に筆者作成
1つ目の目的、つまり学力を向上させるためであれば、時間をかけて自分自身で問題を解くことに価値があり、時間がかかるほど学習効果が期待できますが、2つ目の目的である「怒られないため」においては、宿題が済んでいる状態を作っておく必要があるにすぎないため、愚直に問題を解くことはタイパが悪く、答えを写せば、自分で思考する手間も時間も省けるため、タイパはよくなります。さらに人にやらせれば、自分で答えを写す手間も省けます(※図2)。一方、好きこのんで他人の宿題を代わりに写してくれる人は稀であり、「ジュースおごるから」「500円あげるから」と、本来宿題をするうえでかかるはずのない金銭的なコストを発生させてまでも、時間の効率性を追求する人もいます(※図3)。
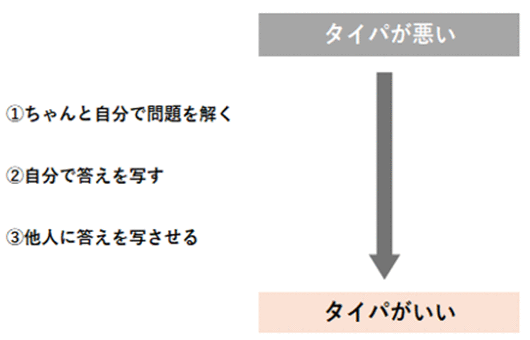
図2 宿題を済ますことに対するタイパ
出所:「タイパの経済学」p.117を基に筆者作成
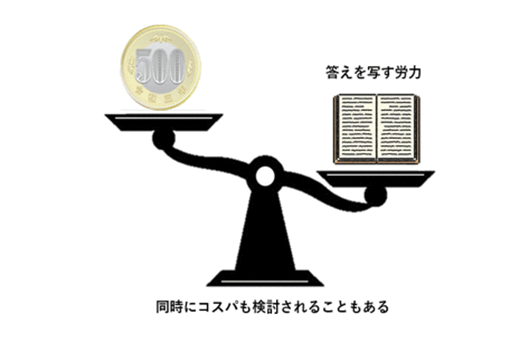
図3 コスパとタイパが同時に検討されることも
出所:「タイパの経済学」p.117を基に筆者作成
効率化のイニシアティブは常に消費者側にある
日常生活において、タイパを重視しないで主体的に消費する場合、その消費結果そのものが目的であるため、消費過程にも意味があるわけですが、タイパを重視する場合、消費過程は特定の状態になるための手段であるため、そこに意味を見出しにくいわけです。そのため、どうすれば手間をかけずに済むのか、また、手間をかけないことでかかる費用はどのくらいなのかと考慮しながら、私たちはタイパを検討しているのです。
労力にかかる時間の短縮としてのタイパにせよ、特定の状態になるための手段としてのタイパにせよ、何をどれだけ、どのようにしてコストをかけてタイパを追求するかは、その人の経済力、時間の余剰、自身の身体的能力など、その人が身を置く環境と、その人がその消費に対してどの程度「タイパ」を追求する必要性を見出しているかどうか、という2つの要件が関わっています。目の前にある問題や目的に対してどの程度尽力するのか、どの程度効率化を目指すか、そのイニシアティブは常に消費者側にあるのです。
(参考文献)
廣瀬涼(2023)『タイパの経済学』幻冬舎 を基に執筆
(ニッセイ基礎研究所 廣瀬 涼)
筆者紹介