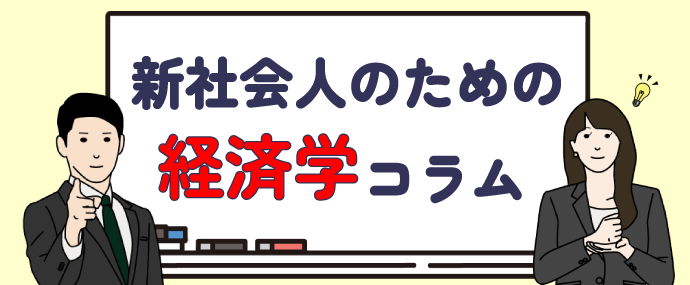第174回 国が進める配偶者手当見直しの目的とは?
新社会人のための経済学コラム2024年8月8日
配偶者手当の見直しが目指す就業調整の解消

配偶者手当とは、企業が配偶者のいる従業員に対して支給する手当です。2023年の人事院勧告によると、扶養家族が配偶者のみ(子どもなし)の従業員に対し、平均12,744円(月額)が支給されていました。高度経済成長期に普及し、2009年(※1)には、約74.7%の企業が制度を有していました(図表1)。
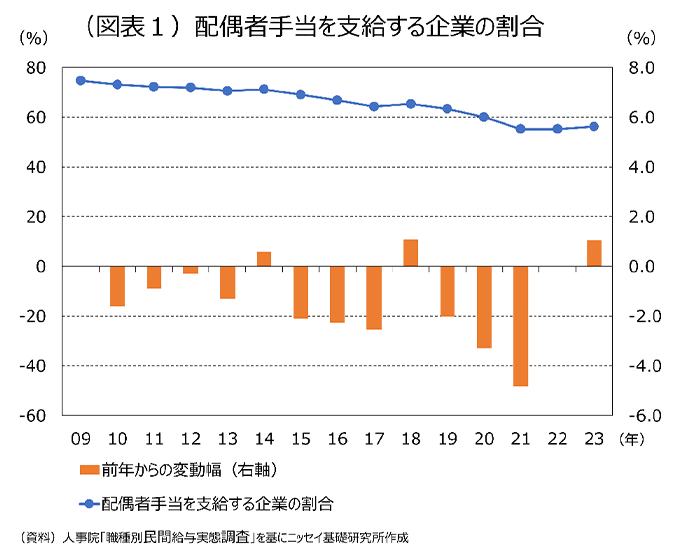
しかし、2023年9月に厚生労働省が発表した年収の壁・支援強化パッケージは、企業の配偶者手当を問題視しています。同パッケージは、社会保険料に関する年収の壁(106万円・130万円の壁)の解消推進と、企業に対する配偶者手当の縮小や廃止(以下、「見直し」)を求めるものです。その目的は、会社員の配偶者など、被扶養者(第3号被保険者)による就業調整の解消です。
被扶養者は、一定額以上の収入がなければ、基本的に社会保険料の負担がありません。しかし、もしパートタイム等の非正規労働に従事し、収入が一定額を超えると社会保険料を支払う必要があります。こうした収入のボーダーラインを年収の壁(※2)といいます。特に、厚生年金保険・健康保険料の支払いが発生する106万円の壁や、国民年金保険・国民健康保険料の支払いが発生する130万円の壁を超えると、労働時間を増やしても手取りが減少する、手取りの逆転現象を招くことがあります(※3)。
年収の壁は、手取りの逆転を避けるために就業時間を調整する、いわゆる就業調整の要因となっています(図表2)。2021年時点で、パートタイム・有期雇用者(有配偶者)のうち、男性の6.9%、女性の20.2%が就業調整を行っていました(※4)。
また、配偶者手当も実質的な年収の壁として機能しています(図表2)。配偶者手当は、配偶者の年収が103万円(※5)、または130万円以下を受給要件とするケースが多く、手当の打ち切りと手取りの逆転を避けるために、就業調整が行われやすいのです。
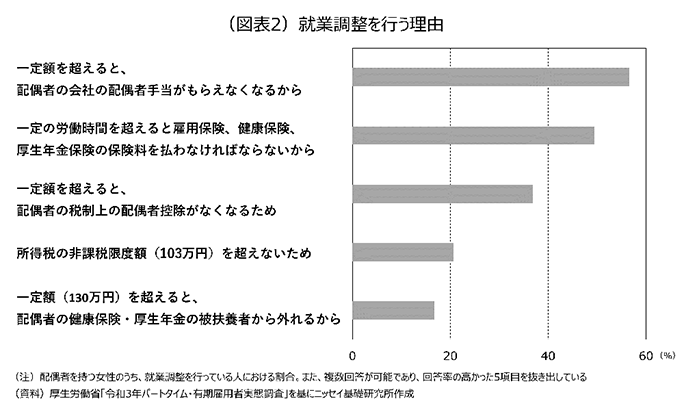
少子高齢化により生産年齢人口(15歳~64歳)が減少する中、働く意思があったとしても働き控えを招く状況は、人手不足を悪化させ日本経済の成長を妨げます。このため、年収の壁・支援強化パッケージは年収の壁の解消と併せて、企業の配偶者手当見直しを促進しているのです。
国の先導と社会の変化によって、見直しは加速
企業も配偶者手当を見直す方向に動いています。配偶者手当を支給する企業は、2023年時点で約56.2%にまで減少しました(図表1)。こうした動きの主な背景には、国の先導と社会的ニーズの低下という2つの要因が考えられます。
国の配偶者手当に関する働きかけは、第2次安倍政権の女性活躍政策で積極化し、現在まで続いています。その中でも、特に企業の見直しに影響を与えたのは、2014年頃から検討を始め、2016年の人事院勧告で決定した、国家公務員の配偶者手当の見直しです。国家公務員の給与は民間準拠(※6)が原則ですが、民間への波及を期待して国が先導する形で実施されました。実際、2016年以降、見直しを予定する企業や廃止する企業は増加しており、政策には一定の効果があったと考えられます(図表1、3)
加えて、配偶者手当という制度自体が時代にそぐわなくなってきています。配偶者手当は、受給要件からも分かるように、世帯主が配偶者を扶養する家族モデルが前提となっています。しかし、共働きの普及や未婚化・晩婚化により、手当の対象者は少なくなっており配偶者手当の社会的ニーズが低下していることが分かります(図表4)
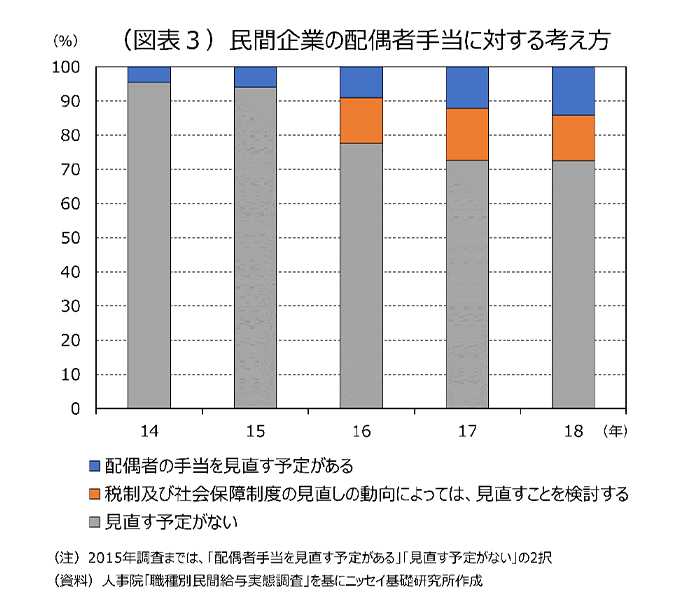
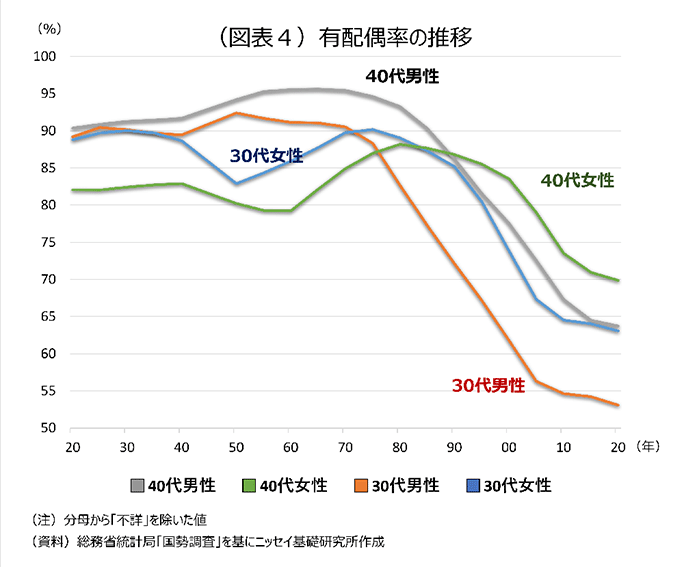
期待される前向きな見直し
とはいえ、配偶者手当の見直しは手当を受けている人にとって収入が減少することを意味することから、労使間の合意なく見直しを行えば、労働契約法で禁止される労働契約の変更にあたる可能性が指摘されています(※7) 。また、見直しが単なるコスト削減に留まるならば、構造的賃上げを掲げる岸田政権の取り組みにも逆行します(※8) 。
だからこそ、見直しにあたっては、労使間の丁寧な対話と労働者の負担を考慮した対応が必要です。対応例としては、見直しを段階的に行う激変緩和措置や、見直しと併せた子ども・介護手当などの拡充、基本給の増額などが挙げられます。見直しは、従業員ファーストという視点で実施されることが望ましいでしょう。
(参考文献)
厚生労働省. 「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(令和6年4月改訂版). 2024-04-25
-
(※1)筆者が、人事院勧告および、人事院「扶養手当の在り方に関する勉強会(第1回)資料」(2015-11-09)にて確認できた限り、2009年以降の数値が公開されている。
-
(※2)なお、106万円、130万円の壁の他に、100万円(住民税の支払いが発生)、103万円(所得税の支払いが発生)、150万円(配偶者特別控除額の縮小開始)、201.6万円の壁(配偶者特別控除額が0になる)など、税に関する年収の壁も存在する。ただしこれらの年収の壁を越えたとしても、手取りの逆転はほとんど発生しないことが指摘されている。
小黒一正.「『年収の壁』の真偽と現行年金制度の歪み」.東京財団政策研究所. 2023-11-06 -
(※3)被扶養者には106万円または130万円の壁のどちらかが適用される。106万円の壁を超えた場合でも、勤める企業の従業員数や週の所定労働時間によっては、上記保険への加入義務が生じない場合がある。この場合に、被扶養者は130万円の壁を意識することになる。
-
(※4)厚生労働省 令和3年パートタイム・有期雇用雇用労働者総合実態調査
-
(※5)配偶者手当の受給要件をいわゆる103万円の壁に合わせていると考えられる。
-
(※6)常勤の国家公務員の給与水準を常勤の民間企業従業員の給与水準と均衡させること.
人事院勧告. 人事院HP .(2024-06-27参照) -
(※7)厚生労働省. 「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(令和6年4月改訂版). 2024-04-25
-
(※8)経済財政運営と改革の基本方針2024 ~賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現~. 内閣府HP .2024-06-21.
(ニッセイ基礎研究所 河岸 秀叔)
筆者紹介