【一覧表付き】介護保険サービスの種類とは。
サービス内容と利用料金を解説
病気/ケガ
2023.05.23

日本には、介護サービスを受けられる介護保険制度が存在します。しかし、「介護保険ではどのようなサービスが受けられるのか」「どのくらいの費用がかかるのか」気になる人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、介護保険サービスの種類や自己負担割合などをわかりやすく解説します。また、介護保険サービスを利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。介護サービスを受ける条件や申請方法もあわせて解説するので、万が一のときに備えましょう。
介護保険サービスとは

日本では高齢化や核家族化に加え、介護離職問題が悪化の一途をたどっています。
これらの問題を受け、介護に関わる人を社会全体で支えることを目的として、2000年に介護保険制度が創設されました。制度創設により、介護が必要になった人は介護保険を利用してサービスを受けられるようになっています。
介護保険制度は各市町村や特別区が主体となり、国がサポートする形で運営されています。国民には40歳以上になると被保険者として加入し、毎月介護保険料を納めることが義務づけられました。国民が納める保険料は、介護保険制度を運営していくうえで重要な財源になります。
介護サービスが受けられる被保険者は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者の2つに区分されています。
| 第1号被保険者 | 65歳以上の人 |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 40~64歳までの医療保険に加入している人 |
第1号被保険者がサービスを利用するためには、要支援状態または要介護状態のいずれかの介護認定を受ける必要があります。
第2号被保険者は、介護保険の対象である「特定疾病」によって介護が必要と認定された場合に限り、サービスを利用可能です。
要介護状態・要支援状態とはどんな状態?
要介護状態区分別の状態像
(80%以上の割合で何らかの低下が見られる日常生活能力(※))

- ※全74項目の要介護認定調査項目において、
- ・介助の項目(16項目)で、「全介助」または「一部介助」等の選択肢
- ・能力の項目(18項目)で、「できない」または「つかまれば可」等の選択肢
- ・有無の項目(40項目)で、「ある」(麻痺、拘縮など)等の選択肢
を選択している割合で80%以上になる項目について集計
- 注1)要介護度別の状態像の定義はない。
- 注2)市町村から国(介護保険総合データベース)に送信されている平成26年度の要介護認定情報に基づき集計(平成28年度2月15日時点)
- 注3)要介護状態区分は二次判定結果に基づき集計
- 注4)74の各調査項目の選択肢のうち何らかの低下(「全介助」、「一部介助」等)があるものについて集計
- ※出典:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」P11をもとに作成
要介護状態は要支援と要介護の2種類があり、要支援1~要介護5までの7段階に区分されています。
要支援とは、要介護状態になる可能性がある、あるいは介護状態となることを予防するため、家事や身支度等に支援が必要な状態を指します。要支援は、状態によって「要支援1」と「要支援2」の2種類があります。要支援1は要支援2よりも日常生活能力があり、サポートが必要ではあるものの、比較的自立に近い状態です。
要支援は介護保険制度が創設された当時はなく、要介護状態の予防を目的として、2005年の法改正で新設されたという経緯があります。
要介護とは、日常生活において常に介護を必要とする状態です。要介護には、状態に応じて要介護1~5の5種類があります。要介護の中でも要介護1が最も低く、要介護5が最も高い状態です。
介護保険の対象となる特定疾病は16種類
第2号被保険者は、厚生労働大臣が定める以下の特定疾病がある場合に限り、介護保険の対象になります。
- ・筋萎縮性側索硬化症
- ・後縦靭帯骨化症
- ・骨折を伴う骨粗しょう症
- ・多系統萎縮症
- ・ 初老期における認知症
- ・ 脊髄小脳変性症
- ・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- ・早老症
- ・脳血管疾患
- ・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- ・閉塞性動脈硬化症
- ・慢性関節リウマチ
- ・慢性閉塞性肺疾患
- ・脊柱管狭窄症
- ・ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- ・末期がん
介護保険で利用できる介護サービス一覧表
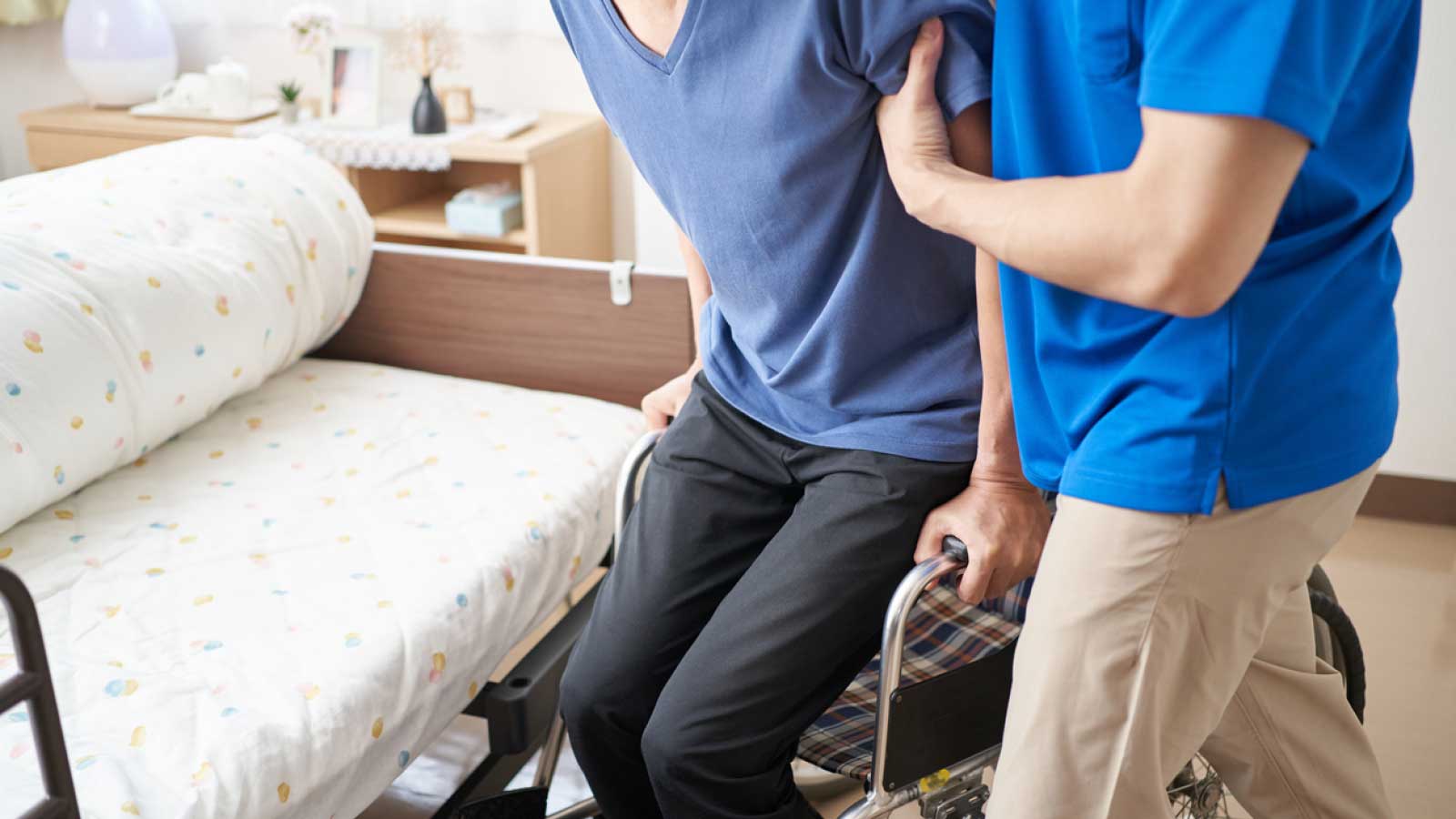
介護保険で利用できる介護サービスは、要介護と要支援のどちらの認定を受けるかで異なります。認定された状態が要介護の場合は介護給付、要支援の場合は予防給付のサービスが利用できます。
要介護1~5と認定された人が利用できる介護サービス(介護給付)
要介護認定を受けた人が利用できる介護サービスは、大きく分けると地域密着型サービス・居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援の4種類があります。
【地域密着型サービス】
地域密着型サービスの内容や料金の目安は、次の通りです。
| サービス名 | 内容 | 利用料金の目安(1割負担) | |
|---|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期的な巡回や随時通報への対応など、介護と看護サービスを必要なタイミングで柔軟に提供する | 【訪問看護サービスを受ける場合】
|
【訪問看護サービスを受けない場合
|
| 夜間対応型訪問介護 | 定期的な巡回や利用者からの連絡により、夜間に介護に必要なサービスを提供する | 【オペレーションセンターを設置している場合】
|
|
| 認知症対応型通所介護 | 通所介護の施設に通う利用者に対し、介護に必要なサービスや訓練を提供する認知症の利用者が通所介護の施設を訪れ、施設では介護に必要なサービスや機能訓練などを提供する | 【社会福祉施設等に併設されていない事業所の場合】
|
|
| 小規模多機能型居宅介護 | 利用者が施設に通うことを中心にして、短期間の宿泊や自宅への訪問などを組み合わせてサービスを提供する | 【同一建物に居住する人に対してサービスを提供する場合】
|
【同一建物に居住する人以外の人に対してサービスを提供する場合】
|
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の利用者を対象にして、専門施設で共同生活を送りながら介護に必要なサービスや機能訓練などを提供する | 【共同生活住居がひとつの場合】
|
【共同生活住居が複数の場合】
|
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員30人未満の施設で介護に必要なサービスや機能訓練などを提供する |
|
|
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム) |
定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で介護に必要なサービスや機能訓練などを提供する | 【従来型個室の場合】
|
|
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて宿泊や訪問に加え、看護師などによる「訪問(看護)」を組み合わせて一体的なサービスを提供する | 【同一建物に居住している場合】
|
【同一建物以外に居住している場合】
|
【居宅サービス】
居宅サービスの内容や料金の目安は、次の通りです。
| サービス名 | 内容 | 利用料金の目安(1割負担) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問サービス | 訪問介護 (ホームヘルプ) |
訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、介護に必要なサービスを提供する | 【身体介護】
|
【生活援助】
|
【通院時の乗車・降車等介助】 99円
|
| 訪問入浴介護 | 看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、入浴介助をおこなう | 【全身入浴の場合】1,260円/回 | |||
| 訪問看護 | 看護職員が利用者の自宅を訪問し、主治医の指示にもとづいて療養上のサポートや診療の補助をおこなう | 【訪問看護ステーションから訪問する場合】
|
【病院または診療所から訪問する場合】
|
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する場合】 2,954円
|
|
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションをおこなう | 20分以上:307円/回 | |||
| 通所サービス | 通所介護(デイサービス) | 利用者が通所介護の施設に通い、施設では日常生活上のサポートや機能訓練などの介護サービスを提供する | 【通常規模の事業所の場合】
|
||
| 短期入所サービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
利用者が介護施設に短期間滞在し、施設では日常生活上のサポートや機能訓練などの介護サービスを提供する
|
【併設型・多床室の場合】
|
||
| 短期入所療養介護 | 利用者が医療機関や介護施設に短期間滞在し、施設では介護に必要なサービスを提供する
|
【介護老人保健施設での介護予防短期入所療養介護費(I)(iii)多床室・基本型の場合】
|
|||
【施設サービス】
施設サービスの内容や料金の目安は、次の通りです。
| サービス名 | 内容 | 利用料金の目安(1割負担) | |
|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 利用者が介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入居し、施設では必要な介護サービスを提供する | 【介護福祉施設サービス費(従来型個室)の場合】
|
|
| 介護老人保健施設(老健) | 利用者が介護老人保健施設に入居し、施設では必要な介護サービスを提供する | 【介護保健施設サービス費(I)(iii)多床室・基本型の場合】
|
【ユニット型介護保健施設サービス費(I)(i)ユニット型個室・基本型の場合】
|
| 介護療養型医療施設 | 利用者が介護療養型医療施設に入居し、施設では必要な医療・介護サービスを提供する | 【療養型介護療養施設サービス費(I)(iv)(多床室)(療養機能強化型A)(看護6:1、介護4:1)の場合】
|
|
【居宅介護支援】
居宅介護支援は、介護支援専門員が利用者一人一人の環境に応じたケアプランを作成し、適切な介護サービスが受けられるよう、各種手続きを代行してくれるサポートサービスです。
例えば利用者が通所サービスの利用を希望する場合は、施設を紹介してもらえます。
要支援1~2と認定された人が利用できる介護サービス(予防給付)
介護予防サービスは、要支援1・2の認定を受けた方に対するサービスで、利用者が要介護状態になることを防ぐ目的で行われます。
介護サービスは、大きく分けると地域密着型サービス・介護予防支援・介護予防サービスの3種類があります。
【地域密着型予防サービス】
地域密着型予防サービスの内容や料金の目安は、次の通りです。
| サービス名 | 内容 | 利用料金の目安(1割負担) | |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型通所介護 | 利用者が施設を訪れ、施設では介護に必要なサービスや機能訓練を提供する | 【社会福祉施設等に併設されていない事業所の場合】
|
|
| 小規模多機能型居宅介護 | 利用者が施設に通うことを中心に、短期間の宿泊や自宅への訪問などを組み合わせてサービスを提供する | 【同一建物に居住する人に対してサービスを提供する場合】
|
【同一建物に居住する人以外の人に対してサービスを提供する場合】
|
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の利用者を対象に、専門施設で共同生活を送りながら介護に必要なサービスや機能訓練を提供する | 【共同生活住居がひとつの場合】 要支援2:760円
|
【共同生活住居が複数の場合】 要支援2:748円
|
【介護予防支援】
例えば利用者が通所サービスの利用を希望する場合は、施設を紹介してもらえます。
【介護予防サービス】
介護予防サービスの内容や料金の目安は、次の通りです。
| サービス名 | 内容 | 利用料金の目安(1割負担) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問サービス | 訪問入浴介護 | 看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、入浴介助をおこなう | 【全身入浴の場合】852円/回 | ||
| 訪問看護 | 看護職員が利用者の自宅を訪問し、主治医の指示にもとづいて療養上のサポートや診療の補助をおこなう | 【訪問看護ステーションから訪問する場合】
|
【病院または診療所から訪問する場合】
|
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する場合】 2,954円
|
|
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションをおこなう | 20分以上:307円/回 | |||
| 通所サービス | 通所リハビリテーション (デイケア) |
利用者が通所リハビリテーション施設を訪問し、日常生活上のサポートや機能訓練などの介護サービスを提供する |
|
||
| 短期入所サービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
利用者が介護施設に短期間滞在し、施設では介護に必要なサービスを提供する
|
【併設型・多床室の場合】
|
||
| 短期入所療養介護 | 利用者が医療機関や介護施設に短期間滞在し、施設では介護に必要なサービスを提供する
|
【介護老人保健施設(介護予防)短期入所療養介護(I)(iii)(多床室)(基本型)の場合】
|
|||
介護保険の自己負担割合と利用限度

公的医療保険制度には複数の種類があり、それぞれ運営元や加入対象者が異なります。
自己負担の割合は1~3割
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合は、1~3割です。負担割合は、利用者の所得に応じて異なります。
基本的には1割負担ですが、一定以上の所得がある利用者は2~3割負担です。2割と3割のどちらに該当するかは、年間所得の合計によって決まります。
| 負担割合 | 年間の合計所得 |
| 2割 | 65歳以上の方で
|
| 3割 | 65歳以上の方で「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額が単身世帯で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上 |
第2号被保険者や市区町村税非課税世帯、生活保護受給者は、年間の合計所得に関わらず1割負担になります。
居宅サービスの1カ月あたりの利用限度額
訪問介護や訪問看護などの居宅サービスを利用した場合、1カ月あたりの利用限度額が要介護度に応じて定められています。限度額を超えた部分は、すべて自己負担です。
| 要介護度 | 利用限度額(1カ月) | 自己負担額1割(1カ月) | 自己負担額2割(1カ月) | 自己負担額3割(1カ月) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
例えば要介護1で自己負担割合が1割の利用者が、1カ月に16万円の介護サービスを利用した場合、1万6千円分が自己負担になります。
自己負担額が高額になった際は「高額介護サービス費」が利用できる
居宅サービスの場合、1カ月あたりの利用限度額が定められています。そのため、利用状況によっては限度額を超え、全額自己負担しなければなりません。限度額を超えた場合は、高額介護サービス費を利用するのも手段のひとつです。
高額介護サービス費とは、限度額の超過分が介護保険から支給される制度です。申請すると自己負担分の上限が設けられるため、介護サービスを利用する際の負担を軽減できます。
自己負担分の限度額は、利用者個人や世帯の所得によって異なります。
| 認定区分 | 対象者 | 1カ月あたりの負担上限額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 個人:15,000円 |
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 個人:15,000円 世帯:24,600円 |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税で第1段階および第2段階に該当しない人 | 世帯:24,600円 |
| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満の人 | 世帯:44,400円 |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満の人 | 世帯:93,000円 | |
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人 | 世帯:140,100円 |
支給を受けるためには、市町村の窓口で申請する必要があります。
介護サービスの申請方法

介護サービスの利用を希望する場合は、自治体の担当窓口で要介護または要支援認定の申請が必要です。
その後、認定調査員が自宅や施設等を訪問し、心身の状態のヒアリング調査が実施されます。主治医からは、心身の状態を医学的観点からみた意見書を作成してもらいましょう。
原則、申請から30日以内に認定結果が通知され、介護サービスの開始に向けて介護支援専門員がケアプランを作成します。ケアプランとは利用者の環境を考慮し、適切な介護サービスの目標や内容をまとめた計画書です。
介護支援専門員は、利用者が適切な介護サービスを受けられるよう、関係機関と調整をおこないます。準備が整い次第、介護サービスが開始されます。
介護費用に不安がある人は介護保障保険を検討
介護が必要になった場合、日常生活の介助やリハビリテーションなどの介護サービスを受けるだけでは不十分なこともあります。例えば自宅で介護する際には、住宅の改造や介護ベッドを準備するために、まとまった金額が必要です。
公益財団法人生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」によると、一時的な介護費用の平均が74万円、月々の介護費用の平均が8.3万円だったことがわかっています。
- ※出典元:公益財団法人生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」
介護費用の捻出に困ったとき、頼りになるのが民間の介護保障保険です。民間の介護保障保険に加入していれば、介護に関する経済的な負担の軽減につながります。
まとめ
日本には公的介護保険制度があるため、介護が必要になったときにはさまざまな介護サービスを利用できます。ただし、利用するためには、要介護または要支援の認定を受けるなど、一定の条件を満たす必要があります。
介護サービスの費用には自己負担の上限額が設けられていますが、その範囲内で十分なサービスを受けられるとは限りません。将来の経済的な負担が心配な場合は、民間の介護保障保険に加入しておくと安心です。
当記事に記載の内容は2023年3月現在の公的制度に基づいております。
監修者プロフィール
ファイナンシャルプランナー/M・Mプランニング 代表
宮里 恵
保育士、営業事務の仕事を経て、ファイナンシャルプランナー(FP)に。
独身、子育て世代から定年後の方までお金に関する相談を受けて、16年目。
主婦FPとして等身大の目線でのアドバイスが好評で、家計・保険・老後・相続などの個別相談を主に、マネーセミナー、お金の専門家として記事の監修、テレビ取材なども受けている。
- ※当社から株式会社アイレップに依頼し記事を執筆していただいたものです。
保険選びにお悩みの方へ
生25-3401,営業企画部




