企業の福利厚生としての保障準備のポイント
高度経済成長期に基礎が整った日本企業の福利厚生制度は、終身雇用、年功序列といった日本型雇用システムとともに、従業員の安心感、勤労意欲を高め、企業の発展を支えてきました。
その後、企業の福利厚生制度は、さまざまな環境変化を受けて、社宅・寮といった生活環境(「ハコ」分野)の整備から、直接従業員を支援する「ヒト」分野にその重点がシフトしつつあります。
従業員と家族の生活保障制度は、「ヒト」分野における重要施策です。費用負担の観点と、4つの保障分野・財産形成の組合せから成り立っています。
その中から、社会保障の上乗せとしての企業の福利厚生制度である「企業保障制度」ならびに「自助努力支援制度」の見直しについて考えてみましょう。
横にスクロールしてご確認ください
| 社会保障制度 【法定】 (企業・従業員ともに負担) |
企業の福利厚生制度 | 個人の自助努力 (個人負担) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 企業保障制度 【企業独自制度】 (企業負担) |
自助努力支援制度 【企業が提供する「場」】 (従業員負担) |
||||
| 保障分野 | 死亡保障 |
|
|
|
|
| 所得保障(休業時・失業時) |
|
|
|
|
|
| 医療保障 |
|
|
|
|
|
| 老後保障 |
|
|
|
|
|
| 財産形成 |
|
||||
企業保障制度および自助努力支援制度の役割
重要性を増す企業保障制度
少子高齢化の進展に伴い、各種の社会保障は給付と負担のバランスが見直されており、従業員とその家族にとって「企業保障」の役割は、社会保障を補完する意義からも一層重要性を増しています。
企業保障制度と自助努力支援制度
企業の福利厚生制度には「企業保障制度」および「自助努力支援制度」がありますが、企業負担による「企業保障制度」は、すべての従業員に対して一定水準の保障を提供する性格を持ち、制度の内容や水準などにおいて、企業独自の考え方が表れます。
一方、「自助努力支援制度」は企業が従業員に対して、福利厚生の「場」を提供する制度です。企業は「自助努力支援制度」を整備するにあたり、従業員が「社会保障」や「企業保障」で不足する部分を、合理的にかつ有利な条件で準備することができるよう設計することが大切です。
生活保障制度の見直しの視点
再構築にあたってのコンセプト
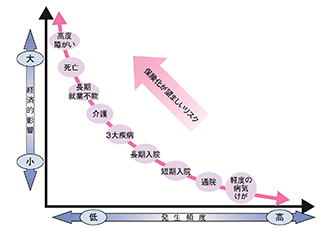
リスクの発生頻度と経済的影響(イメージ)
従業員と家族の生活保障における企業の福利厚生制度の再構築にあたっては、その発生頻度や経済的影響を考慮し、メニューを検討することが重要です。特に、自助努力支援制度については、従業員自らの意思で選択することからも、従業員のニーズに合わせ、以下の点に留意して制度構築を行うことが大切です。
- (ⅰ)シンプル(わかりやすさ、利用しやすさ)
- (ⅱ)リーズナブル(合理性、コストメリット)
- (ⅲ)プライオリティ(優先度※)
- ※優先的に保険化すべき自助努力支援制度として、発生頻度が低く、経済的影響の大きいものに対して準備すべきとする考え方があります。
企業の福利厚生制度(生活保障)の対象拡大
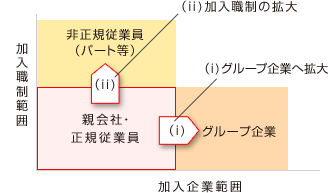
企業の福利厚生制度(生活保障)の対象範囲
企業グループ内での人事交流が多くなり、また、非正規従業員の割合が増加していますが、福利厚生制度を、
- (ⅰ)「グループ企業へ拡大」
- (ⅱ)「非正規従業員へ拡大」
することにより、グループ全体のすべての従業員が制度のメリットを享受できるようになります。その結果、グループへの帰属意識の向上に加え、従業員の間で一体感が生まれるなど、ダイバーシティ・マネジメントの観点からも望ましいといえます。また、制度のスケールメリット拡大も期待できます。
